人間健康研究科教員一覧

岡田 忠克 教授
専門分野
社会福祉政策
ソーシャルアドミニストレーション
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- 健康福祉研究
社会福祉政策研究
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- 人間健康特殊演習I
人間健康特殊演習Ⅱ
人間健康特殊演習Ⅲ
人間健康特殊演習Ⅳ
人間健康特殊演習Ⅴ
人間健康特殊演習Ⅵ
研究概要
現代社会において社会福祉政策は国民生活と切り離せないものになっている。現在の研究テーマは、社会福祉政策を方向づけ、制度を成り立たせている福祉の概念・価値・背景について研究を進めている。とりわけ歴史的背景に重点を置き、現代社会における福祉制度の意義や理念、福祉国家の形成と発展について研究を進めている。

小田 伸午 教授
専門分野
スポーツ科学
運動制御学
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- 人間健康研究
身体運動学研究
運動の理論と実践研究
地域連携課題実習Ⅱ
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- 学社連携スポーツ教育論特殊講義
人間健康特殊演習Ⅰ~Ⅵ
研究概要
人の日常生活やスポーツにおける身体運動の運動制御のメカニズムを探り、その動作の実践における主観性との対応を考察し、客観性と主観性の二つの世界を総合化することに取り組んでいる。運動制御の自然科学的メカニズムは、主に筋神経系分析、動作学的分析から探究する。動作の実践における主観性は、動作者の動作イメージや動作感覚について聞き取り調査などを通じて記述する。動作者の科学的データに主観性データを添えて、両者を照合し、客観と主観を総合した新たな身体運動学を構築する。

神谷 拓 教授
専門分野
体育科教育学
スポーツ教育学
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- 健康マネジメント研究
スポーツ教育学研究
生涯スポーツ教育研究
地域連携課題実習Ⅰ
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- 学社連携スポーツ教育論特殊講義
人間健康特殊演習Ⅰ~Ⅵ
研究概要
学校で行われる体育・スポーツを、授業場面だけに限定せずに、教科外体育や課外体育を含んだカリキュラム論の観点から捉えて研究を続けてきた。とりわけ学校卒業後のスポーツライフ・クラブライフとの接続に関心があり、理論研究と実践研究を往還しながら展望を切り開いていくことを大切にしている。

河端 隆志 教授
専門分野
環境生理学
運動生理学
体力医学
スポーツ科学
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- 運動環境生理学研究
運動の理論と実践研究
地域連携課題実習Ⅱ
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- アダプテッドスポーツ指導論特殊講義
人間健康特殊演習Ⅰ~Ⅵ
研究概要
ヒトは重力のもとに身体活動を通して生存している。生体は様々に変化する環境の中にありながら、その重要な機能(体温調節、体液の浸透圧バランスなど)をほぼ一定のレベルに維持(恒常性、ホメオスタシス)することにより、環境の変化に対処して生存している。そして、運動・スポーツといった能動的な身体運動では、生体はさらに高次の調節機能が要求される。特に長期に及ぶ環境の変化(トレーニングも含む)に対して、生体の体制を変化し、その独自性を保持して生存している状態が適応である。運動・環境生理学の目的は、その適応のメカニズムを解明し、それにより健康およびスポーツ・パフォーマンスの向上のための諸条件を明らかにすることにある。

志岐 幸子 教授
専門分野
感性学
スポーツ感性学
感性教育
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
担当科目
- M:
- 健康心理学研究
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B
研究概要
「感性」は、従来の科学的分析やデータでは得られない情報を得る直感や想像力、創造性、美意識などに関わる内的感覚を含む内的知性のことである。現在、関心を持っている研究内容は、スポーツや芸術、科学など様々な分野でトップパフォーマンスを生む感性と「ゾーン」の他、東洋思想やファンタジー、マインドフルネスの概念を活用した感性教育の具体的方策である。

西山 哲郎 教授
専門分野
スポーツ社会学
身体文化論
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- スポーツ社会学研究
人間健康テーマ研究Ⅰ
地域連携課題実習Ⅰ
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- 学社連携スポーツ教育論特殊講義
人間健康特殊演習Ⅰ~Ⅵ
研究概要
スポーツを通じた地域貢献や、スポーツ自体の新しい楽しみ方を提案する「スポーツプロモーション」を教育・研究の一つの柱とする。「するスポーツ」より「みるスポーツ」や「ささえるスポーツ」に重点を置く関係から「スポーツジャーナリズム」も研究テーマにしている。さらに、社会学的な観点から現代社会における身体の意味や意義(の変化)について考えることも並行して行いたい。
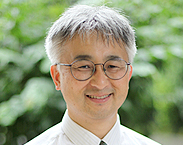
村川 治彦 教授
専門分野
身体教育学
応用健康科学
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- 健康人間学研究
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- 学社連携スポーツ教育論特殊講義
人間健康特殊演習I〜VI
研究概要
「身体」は心理学、社会学、宗教学、哲学、医学、教育学、看護学など多様な分野にまたがるキーワードである。そのなかで、一人称の観点から体験する「からだ」をキーワードに、心理、福祉、教育、看護、医療など対人援助領域における身体性を基盤としたケアのあり方を研究の柱としている。また、体験と言語の関係に注目し、実践を通した経験を意味のある形で言語化し記述する新たな質的研究法の構築に関心がある。

森 仁志 教授
専門分野
文化人類学
文化史
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- 健康調査研究法Ⅰ
身体文化研究
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- アダプテッドスポーツ指導論特殊講義
人間健康特殊演習Ⅰ~Ⅵ
研究概要
現在の研究テーマは次の二つである。①スポーツの国際交流史:日米野球交流においてハワイの日系二世が果たした役割に関する文化史的研究。②家族の比較文化論:家族の起源と変容に関する人類学的研究。これらのテーマを中心に、多様な身体をもつ個人(ジェンダー、セクシュアリティ、人種・エスニシティ、健常者/障がい者など)の包摂(つながり)と排除(分断)のメカニズムを軸に研究に取り組んでいる。
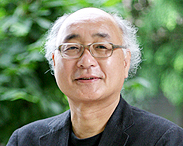
森下 伸也 教授
専門分野
ユーモア学
社会学
担当科目
- M:
- 人間健康研究
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- コミュニティ健康福祉論特殊講義
人間健康特殊演習Ⅰ~Ⅵ
研究概要
「ユーモア学の鬼」を自称する日本笑い学会会長。他の追随を許さぬ笑い好きにして、笑いとユーモアなら何でもござれのオールラウンドプレーヤー(のつもり)。とくに得意は、(1)笑いの哲学、(2)ユーモアの思想史、(3)笑いの日本文化論。(1)は「ひとはなぜ笑うのか」に関する原理論的探究、(2)は哲学者は笑いをどう論じてきたかの歴史的研究、(3)は「日本の笑い文化は世界一」を立証するための「笑い祭」を中心とした実証的研究。もう一つの得意は社会学の外国文献の翻訳で、これまでP.バーガーはじめ多数の翻訳があり、その(自笑)職人芸を、青年たちに大いに伝授したがっている。来たれユーモリスト、来たれ翻訳志望者!

山縣 文治 教授
専門分野
子ども家庭福祉
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- 人間健康研究
子ども家庭福祉研究
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- コミュニティ健康福祉論特殊講義
人間健康特殊演習I〜VI
研究概要
社会福祉学を基礎とし、子ども家庭福祉分野でさまざまな研究や実践をしている。主な課題は、社会的養護、子ども虐待、子育て支援、夜間保育などで、方法としては、フィールドワーク、政策分析、などを用いている。

涌井 忠昭 教授
専門分野
スポーツ科学
応用健康科学
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- 健康行動学研究
健康マネジメント研究
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- アダプテッドスポーツ指導論特殊講義
人間健康特殊演習Ⅰ~Ⅵ
研究概要
研究分野は、レクリエーション、子どもの体力向上、総合型地域スポーツクラブ、障がい者スポーツ、介護労働者(介護者)の生体負担に関する研究と多岐にわたります。具体的には、レクリエーション活動が対象者の心身に及ぼす影響について研究しています。また、子どもの体力向上、総合型地域スポーツクラブおよび障がい者スポーツに関しては、地域での実践活動を通して研究を行っています。さらに、介護労働者(介護者)の生体負担に関しては、介護職員、ホームヘルパーまたは在宅介護者の身体的・精神的負担や腰痛について研究を行っています。

弘原海 剛 教授
専門分野
スポーツ科学
運動生理学
運動処方
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
- D:
- 博士課程後期課程
担当科目
- M:
- 健康運動生理学研究
地域保健活動研究
地域連携課題実習Ⅲ
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B - D:
- コミュニティ健康福祉論特殊講義
人間健康特殊演習Ⅰ~Ⅵ
研究概要
①「糖質飲料水摂取が運動パフォーマンスに及ぼす影響」:いわゆる"スペシャルドリンク"と呼ばれる運動中の栄養補給や疲労回復に効果的なドリンクの開発研究
②「高齢者を対象とした認知症予防研究」:認知症予防体操と脳領域活性を促す可能性のある様々な方法との効果的な組み合わせに関する研究

谷所 慶 准教授
専門分野
トレーニング科学
コーチング学
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
担当科目
- M:
- 健康トレーニング研究
人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B
研究概要
さまざまなトレーニング方法や運動指導方法が身体や運動パフォーマンスにどのような影響を及ぼすのか?競技力向上を目的としたアスリートのトレーニングのみならず、児童期のスポーツ活動と発育発達について、あるいは成人期のスポーツ活動と健康について、トレーニング科学とコーチングの観点から研究しています。また運動の啓発活動がどの程度健康や体力の維持向上に影響するのか、地域の方々と共に調査を実施しています。

西川 知亨 准教授
専門分野
社会病理学
社会的相互作用論
福祉社会学
担当課程
- M:
- 博士課程前期課程
担当科目
- M:
- 人間健康演習(1)A・B
人間健康演習(2)A・B
研究概要
研究分野は、大きく3つに分けることができる。1つ目は、シカゴ学派社会学を通じた社会病理学・社会学史研究である。シカゴ学派社会学の社会調査方法論を整理するなかで、「総合的社会認識」の視点を引き出し、実証的研究の基盤を形作ることを目指してきた。2つ目は、貧困対抗活動が生み出す社会的レジリエンス(柔軟に立て直す力)創発に関する研究である。貧困に対抗する社会活動について、活動が個々人や社会に及ぼす影響に関する研究を行ってきた。3つ目は、「家族福祉の社会学」である。子育て経験などを、理論的・実証的に社会構造や社会福祉につなげる試みを行っている。
