2015年度専門演習紹介(スポーツと健康コース)
テーマ紹介

小田 伸午 教授
テーマ
スポーツにおける主観と客観のずれ
演習内容
自分の関心のあるスポーツ動作を取り上げ、動作構造の客観的把握と、動作実践における主観的把握の両面から考察する。心理的な側面と動作パフォーマンスの関係についての研究、コーチングも研究対象である。
研究手法は、文献研究でもよいし、選手やコーチを対象に調査研究を行ってもよい。動作構造の客観的把握として、動画や地面反力計などの運動解析実験システムを使ったスポーツ科学研究手法を用いることもできる。なお、動作構造の客観的把握と、動作実践における主観的把握のいずれか一つの側面からの研究を行ってもよい。
研究対象として、スポーツ動作を取り上げずに、チームの戦術などの行動面を取り上げてもよい。戦術の構造分析と戦術実践の間のずれを見出し、戦術実践における主観と客観の総合考察でもよい。要は、スポーツの個人や組織のなかにみられる主観的把握と客観的把握の二つの認識の間にみられるずれについて考察し、実践型の思考能力とは何かについて考究する。

河端 隆志 教授
テーマ
ヒトの適応能および運動・スポーツ・パフォーマンスに影響する制限因子を考える
演習内容
何故ヒトは運動をすると、ばてたり、疲れたりするのだろうか。これは、生命維持のために自律的にはたらく生体機能です。スポーツはからだのなかではたらいている制限因子とトレーニングによる適応能との競り合いといってもよいでしょう。
ここでは、自身のこれまでのスポーツ・シーンや運動経験を省みて、ヒトの制限因子についてスポーツ生理学的あるいは環境生理学的視点に立って考察します。アスリート、コーチ、体育指導者を目指す人はパフォーマンスの改善あるいは新たなトレーニング方法が見つかるかもしれません。また、人を対象とした仕事を目指す人は、加齢に伴う体力の変化と運動の大切さについて学ぶことができるでしょう。
地球上という重力の存在するなかでヒトが運動あるいはスポーツをしているときの生体のしくみを如何に定量化し、制限因子のはたらきを解き明かしていく試みをすることが課題です。
身近なスポーツ・シーンや日常の運動場面における疑問点をテーマとして、何を測定すれば生体の制限因子を定量化でき、その結果を如何に現場に応用することができるかについて考察してみましょう。

雑古 哲夫 教授
テーマ
スポーツとバイオフィードバック
演習内容
本専門演習では、スポーツ競技などで精神的な緊張を抑制することにより競技力を向上させる事の可能なバイオフィードバック(以下:BF)のさまざまな研究手法を輪読、発表し、それらの研究をまとめて独自のBFトレーニングの創作を行う。

杉本 厚夫 教授
テーマ
スポーツと子どもの社会学
演習内容
学校体育や学校運動部、スポーツ少年団などの子どもスポーツ、大阪マラソンや総合型地域スポーツクラブなどの市民スポーツ、プロスポーツやスポーツファンをプロモートするメディアスポーツなど、スポーツの社会現象を社会学の視点から解読する方法を学ぶ。
専門演習1では、研究テーマの設定を行うための現地調査の仕方、仮説の設定のための先行研究の仕方、仮説検証のための社会学方法論について学ぶ。さらに、グループディスカッションによって、共同研究の仕方と意義についても学ぶ。

西山 哲郎 教授
テーマ
スポーツプロモーション、スポーツジャーナリズム
演習内容
スポーツの新しい楽しみ方を提案したり、スポーツ(チーム)の応援を通じて人々の生活を豊かにする方法を考えるのが「スポーツプロモーション」です。
「スポーツジャーナリズム」は、スポーツの歴史的・社会的な広がりを調べて、現状の問題点を批判し、その種目の選手でも気づかない価値を明らかにして、広報することが活動の目的です。
具体的な取り組みは次のとおりです。
スポーツプロモーションに関しては、このゼミはバレーボールVリーグのトップチーム「堺ブレイザーズ」と協力関係がありますので、スポーツプロモーションを実際に経験する様々な活動に参加できます。
スポーツジャーナリズムについては、実践から学ぶため、教員の指導の下、インターネットのブログやSNS、雑誌や新聞記事、広報動画などを作成します。今年は昨年に続いて関西大学体育会クラブの活動を取り上げる予定です。

原田 純子 教授
テーマ
表現とコミュニケーション
演習内容
この演習では、人と人との間に生きる私たちに求められる「表現(力)」と「コミュニケーション(力)」について、身体の体験を通して実践的に学ぶ。
具体的には、各人が持つ創造性を活かしながら、ワークショップの企画、映像資料の制作等々を行う。

三浦 敏弘 教授
テーマ
健康を人間行動学から考える
演習内容
現代社会は、ますます質の高い生き方が求められ、健康で活力のある明るい社会の創造に向け、そのあり方・問題の所在を、人間とスポーツ、身体運動、健康生活等のかかわりを通して総合的に考えなければならない。このゼミでは、スポーツのこれまでを考えることと、同時にスポーツの現象や人間・社会・文化への理解を深めることを目的としています。具体的には、理系分野を視野に入れながら研究志向を身体行動に関する様々な文系分野である生活文化、スポーツ行動や生活設計への応用などが主である。人間のメカニズムと人間行動事象を融合するものである。人間身体行動の実践に結びつける事とスポーツ競技の方法学的アプローチから競技力の向上を目指すようなゼミを考えている。毎週のゼミでは、スポーツに関する事象の分析や論文等の要約、プレゼンテーション、ディスカッションを行い読解力、批判力、論理的な考え方や論文作成などを身につけスポーツに対する見る眼を養う。
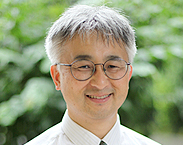
村川 治彦 教授
テーマ
身体文化と健康(主体経験の共有化)
演習内容
この専門演習では、まず担任者が「身体文化と健康」に関する様々な題材を提示し、それを受講生がそれぞれの日常生活の具体的経験を通して考えることを通して、現代社会における健康の問題について多様な観点から考察する力を養っていきます。さらに、各自が関心をもつテーマを選び、関連する文献やインタビュー調査などを通してそのテーマを掘り下げ、プレゼンテーションすることを通して基礎的な研究方法を身につけ、卒業論文執筆に向けての準備を進めていきます。
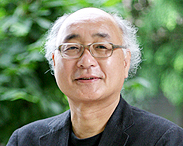
森下 伸也 教授
テーマ
笑いをきわめる
演習内容
- 落語、漫才、狂言、コメディ映画、喜劇、テレビ・バラエティ、ユーモアCM、マンガ、諷刺画、ジョーク、ユーモア文学、冗談音楽、笑い祭りなど、できるだけ多ジャンルのユーモアに触れる。
- 哲学、歴史学、人類学、民俗学、文学、言語学、社会学、心理学、精神医学、生理学、フィールドワークなど、多角的に笑いとユーモアを研究する方法を学ぶ。
- 笑いとユーモアを素材として、自分で研究テーマを発掘し、調査・研究し、それをまとめ、発表するためのスキルをみがく。
- 以上のことを通じて一般的なプレゼンテーションの方法を学ぶ。
- 笑いをとるための実践練習をおこなう。
- 以上のことをふくめ、全般的な就活力アップのためのトレーニングをおこなう。

涌井 忠昭 教授
テーマ
1. レクリエーション組織、レクリエーション活動の効果、2. 子どもの体力向上、3. 総合型地域スポーツクラブとまちづくり
演習内容
本演習(専門演習1および専門演習2)では、卒業論文または卒業研究作成に向けて必要な知識およびスキルの修得を目標に多角的に学習する。
基本的には、1. レクリエーション組織、レクリエーション活動の効果、2. 子どもの体力向上、3. 総合型地域スポーツクラブとまちづくりの3つのテーマの中から、学生自らが興味・関心のあるテーマを選び、個人または少人数のグループで調査・研究を行い発表する。また、必要に応じてテーマに関する講義や演習をなどを取り入れ、学習を深めていく。その場合、授業計画を変更することもある。
なお、上記3つのテーマはあくまでも原則であるので、学生の興味・関心を優先してテーマを決定する。
また、学生自らが主体的に学び、教員はそれを支援するという学習過程を通して、自ら考え行動できる力を養うとともに、多様な「ものの見方」「考え方」を身につけることも本演習の目標とする。

弘原海 剛 教授
テーマ
運動処方・運動生理学
演習内容
本演習(専門演習1および専門演習2)では、卒業論文または卒業研究作成に向けて必要な知識およびスキルの修得を目標に多角的に学習する。
◎本演習のテーマは「健康づくり」である。本演習ではテーマを支える3つの研究領域を置き、演習履修生(ゼミ生)は最低1つを選択し実践する。
(1)実験研究⇒運動生理学の知識を基とした実験的研究にて「健康づくり」に寄与できる新たな“発見”を試みる。
【例】スペシャルドリンクの開発、疲労回復法、体力診断法など
(2)実践研究⇒その人に合った「適度な運動」を科学的に見つけ出し、適切な内容をプログラミングした「健康づくり」のための運動処方を作成する。
【例】老若男女対象とした楽しい健康増進エクササイズ・プログラム、親子健康体操の制作など
(3)調査研究⇒子供~高齢者の「健康」に不可欠な要因をアンケートなどを用いて明らかにする。
【例】「生きがいと健康」、「体力測定結果と生きがいの関係」など
運動生理学の知識をベースに、唄って踊れるエンターティナーな運動指導ができる人材を育てることが夢です。そして、ゼミ生と一緒に地域の健康づくり活動に貢献したいと思っています。

小室 弘毅 准教授
テーマ
教育とは何か?学ぶとはどのようなことか?
演習内容
教育や学びは人の幸せとどう関わるのでしょうか?速く走れるようになることやボールを速く遠くに投げられるようになることによって、私たちはどうなるのでしょうか?そもそも教育や学ぶとはどのような営みなのでしょうか?QOL(クオリティ・オブ・ライフ)という言葉があります。延命だけを目的とする医療に対する反省から生まれてきた言葉です。それでは教育におけるQOLとはどのようなものでしょうか?目先の成果を求めることとは違った、10年後20年後あるいはその人が死ぬ時になってはじめて意味を持つ教育や学びとはどのようなものでしょうか?
このゼミでは、教育や学ぶという営みを根底から問い直すことをしていきます。その際、他の誰かの体験や成長ではなく、他ならぬ自分自身の体験・成長に焦点を当て、考えていきます。自分自身が、本当の意味で成長するとはどのようなことなのか、体験的に考えていけたらと思っています。

志岐 幸子 准教授
テーマ
スポーツ感性学
演習内容
20世紀が科学技術の発展を象徴する一方でその限界を実感した時代でもあったのに対し、21世紀は「感性の時代」と言われている。「感性」は感動や一体感と関わるスポーツ等の文化は勿論、日々の生活から大きな組織に至るまで、あらゆる分野で必要とされており、それを「磨く」ということも求められている。しかしながら、「感性」という言葉は、多くの人々によって至るところで使用されているものの、その意図するところは三者三様であり、学術的にも未だ統一されていない。そのため、まず「感性」の定義の統一や理論化、「感性を磨く手法」の理論的構築が急務と思われる。そこで、本演習では、スポーツを含む様々な文化の「感性」を参照にしながら、理論に基づいた「感性」を磨くための実践的手法をチームで開発することを見据え、「感性」について多角的視点から研究・発表することを主たる課題とする。

森 仁志 准教授
テーマ
イノベーションに関する実践的研究
演習内容
イノベーターとは、「世界を変える人」のことです。健康やスポーツをめぐる課題・問題を、これまでになかったような新しいアイデアで解決すること、これが本演習のテーマとなります。
具体的な課題は、各自が関心に基づいて設定します。たとえば、子供の健康に貢献したい、クラブ活動でのチームワークの向上をはかりたい、あるいは、課題を抱える地域での健康・スポーツ支援サービスや商品の開発改善など自由に設定して取り組みます。
もちろん、イノベーションは、突然生み出されるわけではありません。新たな発想やヒントの発見のためには、人間の行動や心理についての深い観察(フィールドワーク)が必要不可欠です。また、収集した情報を分析・議論する方法や、アイデアをカタチにするための技術も学ぶ必要があります。
本演習では、イノベーションに必要なこれらの技術を習得することにより、将来就職の際に求められる社会人基礎力を養成します。

安田 忠典准教授
テーマ
体験学習
演習内容
…人間とは自然の一部にすぎない、というすなおな考えである。…この自然へのすなおな態度こそ、二十一世紀への希望であり、君たちへの期待でもある。そういうすなおさを君たちが持ち、その気分をひろめてほしいのである。そうなれば、二十一世紀の人間は、よりいっそう自然を尊敬することになるだろう。そして、自然の一部である人間どうしについても、前世紀にもまして尊敬し合うようになるのにちがいない。(司馬遼太郎『21世紀に生きる君たちへ』)
…遠い祖先の時代から祭られてきた神社や森、川、山、岩屋などを心の拠り所とする信仰は、日本人の情緒の基層をなす原動力となった。これが、東洋屈指の繊細さを持つ文化が生み出されるうえで、つよい方向づけをなしたのである。(南方熊楠“The Taboo-System in Japan”)
自然と関わり、向き合いながら暮らしている人々の生活に密着し、様々な体験を通して「互いに尊敬し合う」ような人間の生き方や、日本文化の基底にある繊細な自然観について考察を深める。
