教育過程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
人間健康学部(以下、「本学部」という)では、「学の実化(学理と実際との調和)」の理念のもと、学位授与の方針に掲げる目標を達成するために次の点を踏まえた教育課程を編成します。
- 1
- 教育内容
- (1)
- 教養教育
- ア
- 体験学習を取り入れた少人数教育(「スタディスキルゼミ」)を用いて、学習態度の醸成とコミュニケーションスキルの獲得を目指す。
- イ
- 社会で活躍するために必要な広い知識・視野と柔軟な思考を育成するために、共通教養教育として自己形成科目群や実践科目群等を配置し、総合的な人間力を養う。
- ウ
- 異文化を理解し、異なる意見を持つ人々の立場に立って考えることができる能力、および外国語によるコミュニケーション力を育成する。
- (2)
- 専門教育
- ア
- 人間健康学の体系的な知識を幅広く学ぶ「基礎科目」を通して、専門的な学びへの転換を図る。
- イ
- 2年次からは「スポーツと健康コース」または「福祉と健康コース」に分属し、さらに専門性を深め、総合的なアプローチの視点を身につけるための「応用科目」(各コース共通、各コース別)を置く。また2コースを有機的に連携させることを目的とした「連携科目」を置き、実践的な学びを深める。
- ウ
- 健康への好影響が実証されている「笑い」について、多角的にアプローチする「ユーモア学プログラム」を置き、人間の健康を多角的にとらえることを学ぶ。
- エ
- 上記科目で学び得たものを実際的な研究テーマとして設定し、少人数指導によりきめ細かい指導のもとに課題を探求する「演習科目」、専門資格取得のための「選択科目」および「自由科目」に分けられ、基礎から応用への学びが連続する段階的な教育体系としている。
- オ
- 本学部の教育の要であり、必修となっている「演習科目」では、導入演習(1年次)、基礎演習(2年次)、専門演習(3年次)、卒業演習(4年次)を設置し、アカデミックスキルの獲得から専門性の応用まで、一貫した少人数指導を行っている。4年次の卒業演習においては、卒業論文もしくは卒業研究のいずれかを課題とし、学生の個別の研究テーマにもとづく論文指導や卒業制作、研究発表のための指導を行う。
- 2
- 教育評価
- (1)
- 専門演習および卒業演習への円滑な移行を図ることを目的とし、各セメスター終了時には必修科目および語学教育の科目を中心に単位習得状況を確認する。
- (2)
- 4年間の学修成果は、卒業演習および卒業論文または卒業研究によって行う。本学の評価基準を満たしたものを合格とする。


カリキュラムの流れ
人間健康学部のカリキュラムは次のようになっています。
※掲載しているカリキュラムは2019年度のカリキュラムのため、今後変更となる場合があります。
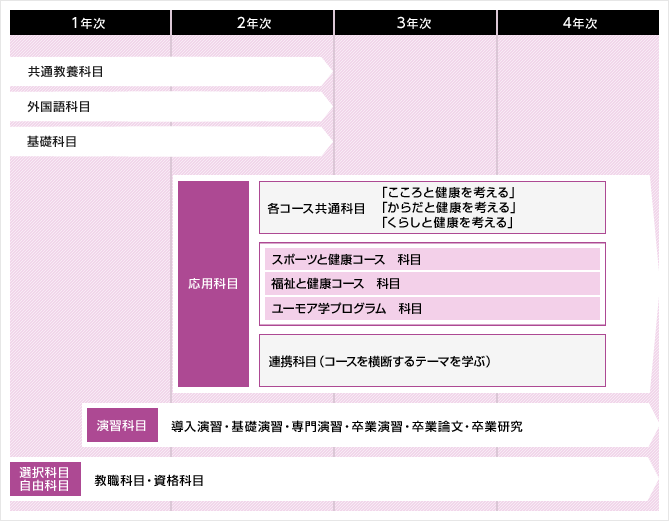
基礎科目1・2年次
幅広い実践力のベースとなる専門知識を1年次から身につけるために、学部に共通する基礎的な専門教育科目を履修します。人間の健康に関する基本的な知識を学ぶことができます。
応用科目(各コース共通|スポーツと健康コース|福祉と健康コース|ユーモア学プログラム|連携科目)2〜4年次
健康に関する視野を広げ、思考を深める科目を配置しています。より専門的、応用的な科目群といえます。
2年次から皆さんは、[スポーツと健康コース][福祉と健康コース]のどちらかを選ぶことになりますが、自コースの科目のみでなく、もう一方のコース科目、各コース共通科目、連携科目などの科目を履修することができます。
演習科目1〜4年次
1年次の秋学期から、演習が始まります。これは、少人数のクラスに分かれ、ゼミ形式で行う授業です。1年次の導入演習では、文章力など基本的スタディスキルを向上させ、ディベートなどを通して大学生活の土台を築きます。2年次の基礎演習では、研究の方法やテーマの見つけかたを学び、研究成果をグループでまとめ、プレゼンテーションを行います。3年次の専門演習では、各自で設定したテーマについて、レポートにまとめるスキルを習得します。4年次の卒業演習では、2,3年次の演習で培った力をもとに、4年間の研究の集大成である卒業論文の執筆や卒業研究の成果発表をしていきます。
選択科目・自由科目1〜4年次
教員免許、司書教諭の資格取得や社会福祉士、健康運動指導士などの受験資格を取得するのに必要な各分野の専門教育科目です。
カリキュラム一覧
人間健康学部では、人間健康学の体系的なカリキュラムのもと、各コースがそれぞれの特色に合わせた学びを提供します。また、コース共通科目を設定することにより、健康に関する多様なアプローチをもち、「基本構想力」「課題探究力」「協調力」「専門応用力」の調和する総合的な人間力を兼ね備え、社会の幅広い分野において活躍できる人材を育成します。
※このカリキュラム一覧は2019年度のものです。
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通教養科目 | スタディスキルゼミ(各テーマ) プロジェクト学習(各テーマ) 健康・スポーツ科学実習a・b 健康・スポーツ科学論 関西大学スポーツ文化論 スポーツ運動学概論 スポーツ社会学概論 スポーツ心理学概論 スポーツ栄養学概論 コーチングの科学 トレーニング科学概論 コンディショニング科学概論 キャリアデザインⅠ(働くこと、生きること) |
キャリアデザインⅡ(仕事の世界) キャリアデザインⅢ(私の仕事) プロジェクト学習Ⅱ(各テーマ) |
||||
| 哲学を学ぶ 日本文学を学ぶ 心理学を学ぶ 社会学入門 日本国憲法 基礎からの情報処理 食を知る 日本の文化と人間を考える 法学を学ぶ 政治学のすすめ 日本の歴史を学ぶ 西洋の歴史を学ぶ 基礎からのマクロ経済学 基礎からのミクロ経済学 確率・統計でものを考える 労働と雇用を考える ビジネスを学ぶ 数学を学ぶ(各テーマ) 身体運動の人間学 共生社会のライフデザイン 笑いとユーモアを科学する 少子高齢化社会を考える オリンピックの共生思想 堺市と関西大学 学校インターンシップ(ステージ1)・(ステージ2)・(ステージ3) |
||||||
| 外国語科目 | 英語Ⅰa・Ⅰb 英語Ⅱa・Ⅱb ドイツ語Ⅰa・Ⅰb ドイツ語Ⅱa・Ⅱb フランス語Ⅰa・Ⅰb フランス語Ⅱa・Ⅱb ロシア語Ⅰa・Ⅰb ロシア語Ⅱa・Ⅱb スペイン語Ⅰa・Ⅰb スペイン語Ⅱa・Ⅱb 中国語Ⅰa・Ⅰb 中国語Ⅱa・Ⅱb 朝鮮語Ⅰa・Ⅰb 朝鮮語Ⅱa・Ⅱb |
英語Ⅲa・Ⅲb 英語Ⅳa・Ⅳb |
英語Ⅴa・Ⅴb(各テーマ) 英語Ⅵa・Ⅵb(各テーマ) |
|||
| 外国人留学生科目 | 日本語Ⅰa・Ⅰb・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳa・Ⅳb 日本事情Ⅰ・Ⅱ 実践ビジネス日本語Ⅰ・Ⅱ キャリアデザインⅠ(日本の社会と企業) キャリアデザインⅡ(日本の就職と働き方) キャリアデザインⅢ(日本の社会で働く) |
|||||
| 専 門 教 育 科 目 |
基 礎 科 目 |
各コース 共通 |
人間健康論 スポーツ生理学 スポーツと健康 社会福祉概論 健康支援の社会システム 身体文化と健康 身体表現と健康 健康の文化史 体育史 こころと健康 衛生学及び公衆衛生学 医学一般 社会調査法 当事者福祉論 精神保健福祉論 臨床心理学 救急安全法 社会福祉政策Ⅰ 社会福祉政策Ⅱ 介護概論 ソーシャルワークⅠ ソーシャルワークⅡ ユーモア学入門 |
|||
| 応 用 科 目 |
各コース 共通 |
<からだと健康を考える> スポーツ原理 スポーツ教育学 スポーツ心理学 運動処方論 グループダイナミクス特別演習 体力科学 臨床バイオフィードバック <こころと健康を考える> 身体教育学 身体表現論 現代スポーツとオリンピズム 武道論 身体の文化人類学 学びの身体技法 人間行動論 <くらしと健康を考える> リハビリテーション論 フィールド調査法 家族福祉論 臨床死生学 |
<からだと健康を考える> スポーツ栄養学 <こころと健康を考える> 身体文化論 舞踊文化論 <くらしと健康を考える> 福祉レクリエーション論 社会福祉調査法 老人・障害者の理解 福祉経済論 |
|||
| スポーツと 健康コース |
スポーツ運動学 スポーツ社会学 スポーツ経営学 学校保健 スポーツ感性学 コーチング論 スポーツ文化論 スポーツ動作の仕組みと制御 レクリエーション支援論 トレーニング論 |
スポーツ方法学 スポーツ医学 生涯スポーツ論 地域スポーツデザイン論 障害者スポーツ論 スポーツ統計学 |
||||
| 福祉と 健康コース |
ソーシャルワークⅢ ソーシャルワークⅣ ソーシャルワークⅤ ソーシャルワークⅥ 高齢者福祉論 子ども家庭福祉論 福祉行財政と福祉計画 障害者福祉論 公的扶助論 地域福祉論Ⅰ 地域福祉論Ⅱ 医療福祉論 |
社会福祉経営論 雇用政策 司法福祉 社会保障論Ⅰ 社会保障論Ⅱ 権利擁護と成年後見制度 社会起業論 |
||||
| 「ユーモア学」 プログラム |
笑いと健康 笑いの文学 笑いの文明史 笑いの民俗学 ユーモアの社会学 笑いの心理学 |
ユーモアコミュニケーション論 | ||||
| 連携科目 | テーマ研究Ⅰ・Ⅱ | |||||
| 演習科目 | 導入演習 | 基礎演習 | 専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ | 卒業演習Ⅰ 卒業演習Ⅱ 卒業論文 卒業研究 |
||
| 選択科目 |
スポーツ方法実習Ⅸ(球技2) 寄附講座(各テーマ) |
スポーツ方法実習I(陸上競技) スポーツ方法実習Ⅲ(器械体操) スポーツ方法実習Ⅶ(ダンス) スポーツ方法実習Ⅷ(球技1) 野外教育実習(野外活動) トレーニング実習Ⅰ トレーニング実習Ⅱ 地域スポーツ演習 健康運動実習Ⅰ 健康運動実習Ⅱ レクリエーション実技Ⅰ レクリエーション実技Ⅱ 身体表現Ⅰ 身体表現Ⅱ 国際健康福祉実習(各テーマ) 野外活動特別演習 運動処方実習 予防医学 相談援助演習Ⅰ 福祉実習指導Ⅰ |
スポーツ方法実習Ⅱ(水泳) スポーツ方法実習Ⅳ(武道1) スポーツ方法実習Ⅴ(武道2) スポーツ方法実習Ⅹ(球技3) スポーツ方法実習XI(球技4) 実技研究 健康運動指導演習 相談援助実習Ⅰ 相談援助実習Ⅱ 社会福祉制度研究Ⅰ 増健科学演習 相談援助演習Ⅱ 福祉実習指導Ⅱ |
相談援助演習Ⅲ 社会福祉制度研究Ⅱ |
||
| 自由科目 | 教職概説 教育原理 |
教育制度論 人権教育論 教育心理学 特別活動論 道徳教育の理論と方法 教育方法・技術論 教育相談論 保健体育科教育法(一)・(二) 学校経営と学校図書館 情報資源組織論 図書館情報資源概論 学習指導と学校図書館 読書と豊かな人間性 情報メディアの活用 |
特別支援教育論 カリキュラム開発論 総合的な学習の時間の指導法 生徒・進路指導論 教育実習事前指導 保健体育科教育法(三)・(四) |
教育実習(一)・(二) 教職実践演習(中等) |
||
