学部教員一覧
スポーツと健康コース

小田 伸午 教授
研究テーマ
健康・スポーツ科学
ゼミ紹介
スポーツ競技力向上の研究や、心理が動作に及ぼす影響、動作修正の主観的コツなど、みずからが研究テーマを決めてグループを作り、意見を交換しながら研究を深め、社会に出て必要とされる問題解決の実践力を養います。

神谷 拓 教授
研究テーマ
体育科教育学・スポーツ教育学
ゼミ紹介
学校の体育授業、体育行事、運動部活動などが行われる理由を、教育学の観点から解明していきます。理論の学習、討論・議論、現場における実践・フィールドワークをくり返しながら、理解を深めていきます。
https://wps.itc.kansai-u.ac.jp/kamiya/
河端 隆志 教授
研究テーマ
運動・環境適応学
ゼミ紹介
スポーツや運動時に、からだでは環境や運動ストレスに対する適応能が働いています。このようなヒトの自立性の調節機能を「全機性」といいます。ここではスポーツシーンや健康に関するテーマを現場から見つけ出し、パフォーマンスの向上や健康増進に関する知識と実践力を養います。

雑古 哲夫 教授
研究テーマ
バイオフィードバック(BF)
ゼミ紹介
BFの手法を活用し、筋電図や発汗量、脳波などの推移から拮抗筋の過緊張を認識する事より、精神的な緊張を抑制し、競技力、競技成績の向上を試みる研究を行います。
http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~zako/
志岐 幸子 教授
研究テーマ
感性学、スポーツ感性学
ゼミ紹介
アスリートや芸術家の「ゾーン体験」に関わる感性の他、日常生活・社会のあらゆる場面、科学・ビジネスなど様々な分野で求められている感性について議論し、生かす方法を研究します。
http://www2.itc.kansai-u.ac.jp/~shiki/
灘 英世 教授
研究テーマ
体験学習、救急安全
ゼミ紹介
体験学習(アドベンチャープログラム)、各種グループワークなどを用いて人と人の関わりや体育教員に求められるものは何か、教員―生徒の関係性の問題を追求します。

西山 哲郎 教授
研究テーマ
スポーツプロモーション、スポーツジャーナリズム
ゼミ紹介
する、みる、ささえる。スポーツの多様な楽しみ方を理解し、問題を分析して、新しい遊び方を発見する。スポーツを通じて人々の生活を豊かにするのが私のゼミの目標です。

原田 純子 教授
研究テーマ
舞踊教育学、舞踊学
ゼミ紹介
多様な表現活動に触れ、「表現力」を磨くとともに、身体表現活動においては「共創(協力して新しい価値を創造する)」をテーマとして、「自分らしい表現」を探求します。

三浦 敏弘 教授
研究テーマ
スポーツを人間行動から考える(人間行動学)
ゼミ紹介
学生の研究テーマは、ヒトのメカニズムと行動事象の融合を導き出すことにあります。身体行動の実践とスポーツ競技の方法学的アプローチから競技力向上をめざします。
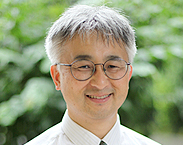
村川 治彦 教授
研究テーマ
からだの体験を探る
ゼミ紹介
スポーツなどを通してこれまで培ってきた能力を、熊野や浅香山など地域コミュニティでの活動を通して、社会人として様々な分野で活躍できる実践知へと一般化することをめざします。

森 仁志 教授
研究テーマ
イノベーション、ソーシャルデザイン
ゼミ紹介
イノベーターとは、「世界を変える人」のことです。健康やスポーツをめぐる課題や問題を、これまでになかったような新しいアイデアで解決するための手法を実践的に学びます。

安田 忠典 教授
研究テーマ
体験学習
ゼミ紹介
アドベンチャープログラム、野外活動、自炊、各種グループワークなどを用いて、人と人、人と社会、人と自然などの関係性の問題を追及します。

涌井 忠昭 教授
研究テーマ
レクリエーション、福祉レクリエーション
ゼミ紹介
レクリエーション、子どもの体力向上、総合型地域スポーツクラブおよび障がい者スポーツをキーワードに学生の興味・関心に応じてテーマを決定し、研究を進めます。

弘原海 剛 教授
研究テーマ
運動生理学、運動処方
ゼミ紹介
運動生理学の知識をベースに「実験系は、疲労回復や持久力向上等に効果的なスペシャルドリンクの開発研究」「実践系は、堺コッカラ体操を軸に地域へ出向き健康サービスを通した生きがい研究」を行っています。

小室 弘毅 准教授
研究テーマ
身心教育学・ホリスティック教育学
ゼミ紹介
こころとからだとは別々のもののように見えて、実はつながっています。そのつながりのあり方を、教育学、心理学を基盤に、身体、人間関係、コミュニケーション、アート、ファッション、建築といった観点から考えていきます。

谷所 慶 准教授
研究テーマ
スポーツのコーチングとトレーニング
ゼミ紹介
どうすれば強くなるのか?どう指導すればゲームが面白くなるのか?ゼミではコーチングやトレーニングの観点から、ヒトとスポーツについて総合的に議論します。
福祉と健康コース

岡田 忠克 教授
研究テーマ
現代社会と福祉問題
ゼミ紹介
ゼミでは「現代社会と福祉問題」をテーマに研究発表をしています。とりわけ貧困問題をキーワードに、政治経済システムとの関連について研究を進めています。
http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~t060017/
所 めぐみ 教授
研究テーマ
地域福祉実践研究、地域を基盤とした福祉教育
ゼミ紹介
誰もひとりでは生きていけません。共に支え合える地域づくりをどうやって進めていくか。関心のある地域や実践をフィールドとして、研究を進めます。

狭間 香代子 教授
研究テーマ
ソーシャルワークの理論と方法
ゼミ紹介
わが国における今日的な福祉的問題を幅広く取り上げます。学生は各自が関心のある福祉的問題を調べて発表し、それらに対する支援方法について討議していきます。

山縣 文治 教授
研究テーマ
子ども家庭福祉
ゼミ紹介
親子の福祉について、できるだけ具体的に考え、行動する力を身につけることを目標にしています。主体は学生であることを大切にしゼミ運営を心がけたいと考えています。

種橋 征子 准教授
研究テーマ
高齢者福祉、介護福祉、福祉経営
ゼミ紹介
社会福祉の制度・政策の問題だけでなく、認知症や障害を持つ方の思いや家族の思い、具体的な支援方法、福祉人材の養成や人手不足の問題など対人援助にかかわる問題について意見を交わし、解決策を検討します。

西川 知亨 准教授
研究テーマ
社会学から考える人と社会のための福祉
ゼミ紹介
社会学の理論や方法を用いて、たとえば「仕事」「家族」「若者」「友人」「教育」「貧困」など、各自が関心を持っている社会現象が、自分や人々の福祉(健康/「健幸」)とどのようにかかわっているのか調べ、考えます。

福田 公教 准教授
研究テーマ
実践的視点から福祉問題を読み解く
ゼミ紹介
国内や外国でのフィールドワークを基に学生の関心に応じてテーマを設定し、現代の福祉問題の理解と問題解決に向けた手法を実践的に学びます。
ユーモア学プログラム
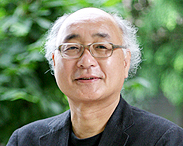
森下 伸也 教授
研究テーマ
笑いとユーモア
ゼミ紹介
「笑いをきわめる」がモットー。笑いとユーモアの理論・実践両面の達人となることをめざして、古今東西の多様な笑いに触れ、おもしろコミュニケーションのスキルを磨きます。

森田 亜矢子 准教授
研究テーマ
人間科学
ゼミ紹介
人が笑うのは、愉快な時だけではありません。苦境にたたされた時や、誰かを励ます時にも笑います。笑う行動を理解することは、人間を理解することでもあります。ゼミでは、様々な行動を手がかりに、人間をみつめ、理解を深めます。
https://wps.itc.kansai-u.ac.jp/wonder/
浦 和男 准教授
研究テーマ
笑いの社会文化論
ゼミ紹介
人間社会のなかで「笑い」が関わるさまざまな現象を多角的に考察し、人間にとって「笑い」とは何か、「笑い」を介して人間と社会はどのように関わるかを追究します。
