座談会2日目(年代:20~30代)

「機材センターが2030年に目指す姿」
- 永田

- 大型プロジェクトなどでは、機電系社員が作業所に配置されることがあり多くの評価を得ています。基礎工事など工事限定での常駐対応を含めて、今後どの分野での施工管理が求められるのか、皆さんの考えを聞かせてください。
- 中江

- 解体工事は施工計画次第でかなり金額が変わります。特に地下の解体工事は、普通に切梁で解体するより、オープンで解体する方がやりやすかったり、そのためには山留の補強が必要になったり、そうした技術や知識を持っている人が詳細に計画を詰めると結構なコストダウンが図れます。機材センターにその役割を担っていただければ非常にありがたいです。
- 熊谷
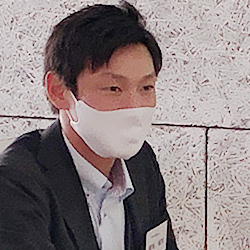
- 解体工事は施工経験者が少ない気がします。協力会社が施工計画を全部やってきてくれるイメージはありますが、逆に任せっきりになっているところが課題でもあります。東京の解体工事で、ガスで切断した金属片が下に落ちて本設ケーブルを燃やす事故がありました。
解体工事で結構ヒヤリハットが起きている中、危険な作業が行われているのではないかと気づける人材を現地に配置することが必要ではないかと思います。機材センターが常駐までする必要はないとは思いますが、気をつけるポイントだとか、届出のアナウンスとか、機電系社員でフォローできるところがあると思います。 - 松原

- せり上げ足場の外部養生がトレンドになりつつある状況の中で、結構そういうものはクレーンで吊るかジャッキで上げるとかいろいろなノウハウがあって、作業所の担当者も経験者が少なくて、誰がノウハウを蓄積するかということになると、やっぱり機材センターが良いのではないかと思います。
- 赤尾

- 作業所の建築担当者は、工事で経験したノウハウの蓄積や展開ができていない気がします。技術部や機材センターがノウハウを蓄積・展開するのは大事なことだと思います。
- 西野
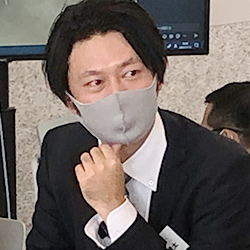
- 機材センターに何が求められているのか、今回の事前アンケートで初めて客観的に考えることができました。それを機械部門として、今後どういう方向に広げていくのかをみんなで議論する場があってもいいなと思いました。かといって、何でもやるとプロフェッショナルにはなれなくて、ちょっと詳しい人間で終わってしまうので、これは絶対機械系社員がやるべきものを絞り出すことが大切だと思います。
- 赤尾

- 私は、機械系社員の方と作業所で一緒に仕事をしましたが、その仕事ぶりを見て、建築系社員として全部できるなと思いました。
- 永田

- 似たような話題になりますが、機電部門として誇れる技術や他社との差別化を図るために強化したいことについて、皆さんの考えを聞かせてください。
- 中江

- 私は杭工事の調達担当で査定をしていますが、施工日数とか歩掛りの設定が難しくて、協力会社が柱状図を見て「ここまでしか掘れません」と言われると、想定で査定をしてしまうことがあります。機材センターと連携していれば、協力会社が言った内容を鵜呑みにせずに適切に査定できると思います。豊田さんにヒアリングしたりすることありますが、全現場でやっているわけではなく、今後は強化していきたいなと思っています。
- 赤尾

- 入札物件とかで、すごく複雑な基礎工事は、機械系社員の方に相談するのですが、その他の工事でも経験豊かな機械系社員の方にもっと話を聞いて意見を取り入れることができれば、更にコストメリットがある工法が提案できるのではないかと思います。
- 松原

- 私は特殊工事の経験が多く、ジャッキアップの日などにマスコミが来て、現場にスポットライトが強く当たるのは特殊工事が多いと感じています。その中核を機材センターが担うことで、社内的な立ち位置も良く、やりがいのある分野だと思います。
また、特殊工事を経験すればするほど、躯体業務に詳しくなっていきます。我々の知識はどちらかというと仮設というか生産側の理解ばかりですが、特殊工事は本設躯体をいじったりするので、構造的な理解であったり、もっと建築の深いところまで理解が入っていきます。特殊工事を経験することで、機材センター全体がベースアップして、しっかり絡んで、更にノウハウを蓄積していければ良いと思います。 - 紅屋
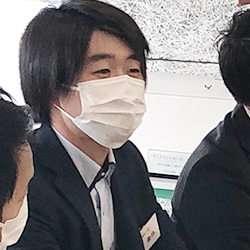
- 私は揚重機械の組立・解体指導や検査・点検を当社社員が実施していることが他社との差別化になっていると感じています。どのくらい危ないかっていうことが一番肌で実感できるというか、機材センターの人が「危ない」というと、本当に危ないと思いますので、危険に対する感性が非常に高いという面では、誇れる技術というか体制だと思います。
- 熊谷
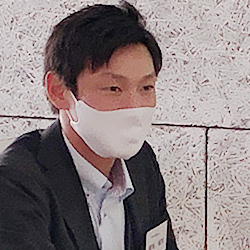
- 作業所長アンケートを見ると、機材センターの基礎工事に対する貢献度は高いと感じました。本設の構造物なので、一緒に苦労してつくった記憶がすごく残っているのだなと思いました。作業所の建築担当者も機材センターの担当者と同等の知識を身につけて、協業してやっていくことが、他社との差別化になると思います。
- 嵯峨

- 私は他社を知りませんが、皆さんの話を聞いて、他社との差別化を図るためには、基礎工事でコスト対応力を強化していくことが必要だと思いました。基礎工事の実績やノウハウは蓄積できていると思いますが、そういう意識を持って仕事をしていないと、大事なデータが埋もれてしまうと思います。
- 永田

- 施工管理や実施計画をする上で、どのようなスキルが求められると思いますか。
- 松原

- 私は総合力が必要だと思います。機電系社員は、機械や電気だけを知っているだけでは全然足りなくて、現場の躯体、仕上げ、土とか、すべてを知っている人と知らない人では雲泥の差があります。それは内勤に入っても顕著に現れて、その人が持つ計画の説得力や深みというのは全然違います。建築担当者がやっているスキルを100%とは言わないですが80%くらいのレベルで、我々は建築会社の社員として身につける必要があると思います。
- 西野
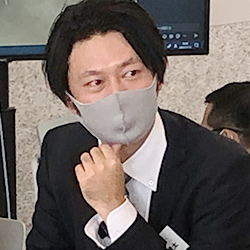
- 我々の強みは、機械を主として建築や設備のことも川上段階から参入して考えながら、計画や実施ができることだと思います。機械を建てたらいいとか、杭をやったらいいというのではなくて、こういう工程で、こういう仕上げだから、こうした方がいいのではないかというように、建築全体を考えた計画や実施ができるスキルを強化していけたら良いと思います。
- 熊谷
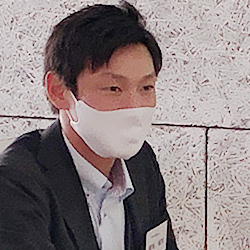
- 私は想像力が必要だと思います。機械に特化した話だけじゃなくて、建築の進み具合だとか、そこで作業する人とか、現場の状況を想像して施工計画をしないと、実施できる計画になってこないので、そういう意味でも建築の知識は必要だと思います。危険予知も、どこまで想像できるかが大事だと思います。
- 赤尾

- 先程も話をしましたが、作業所で一緒に仕事をした機械系社員の方が、作業所での施工管理に必要となる判断力と調整力に優れていると感じて、我々も見習うべきだと思いました。
- 中江

- 私は機材センターの方は専門的な部分が強いという印象があり、専門分野で活躍していただいているイメージがあります。場所打ち杭を機材センターで施工管理してもらいましたが、その知識は非常に高く、大変助かりました。
- 山添

- マネジメント能力、コミュニケーション能力、柔軟さが大切だと思います。やっぱり、我々が作業をして建物を建てていくわけではなく、作業していただく方をうまく調整して、動いていただくことが重要だと思います。
- 永田

- 少し話題が変わりますが、東西機材センターでの人材交流について、皆さんの考えを聞かせてください。
- 熊谷
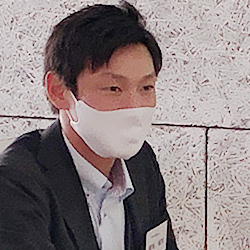
- 東日本機材センターは、一時的に現場に行ったりしますが、基本的には機材センターの中での仕事がずっと続きます。そこで、一度拠点を変えて仕事をすることは、コミュニケーション能力を高めたり、人脈を形成できたり、他のやり方をいろいろ学べるなど、かなり価値があると思います。横田さんが東日本に来られたときにいろいろ教えていただき、是非また一緒に働きたいと何度も思っています。
- 嵯峨

- 私は、東日本機材センターでずっと基礎工事をやっていたので、大阪に行ったとき、免震工事や特殊工事を経験することができたので、仕事の幅を広げられて非常に良かったと感じています。
- 紅屋
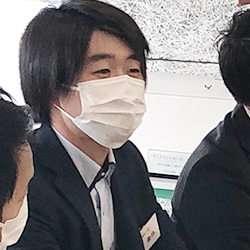
- 保有機械や組立・解体のやり方が違うので、お互いを知るためには交流しても良いと思います。ただし、東西で目指すべきところを統一していかないのであれば、あまりやる意味がないと思います。
また、今回の座談会のように、東西での意見の違いを知ることができて勉強になりますが、自分たちの居場所に戻った時に何も変わらなければ、せっかくの経験が無駄になってしまうと思います。 - 中江

- 調達部でも人材交流をしています。東京から大阪に行った人に話を聞くと「大阪のやり方を知って勉強になったが、大阪と東京は別物で、大阪のやり方は東京では使えない」と言っていました。人材交流することで、お互いのパフォーマンスが上がるのであれば、どんどんやるべきだと思いますが、ただやっているだけで終わっているようであれば、やらなくても良いかと思います。
- 赤尾

- 大阪の技術部計画グループも人材交流をしています。いろいろと話を聞くと「計画のバリエーションが増えた」とか「東京は大規模物件が多くて勉強になった」など、スキルアップになったとの意見が多く、私はやるべきだと思います。
- 山添

- 東西交流だけでは建築業界の考え方になってしまうので、異業種交流をすべきだと思います。異業種の仕事のやり方や考え方を聞ける場があれば、発想の転換ができて新しいアイデアのヒントになるのではないでしょうか。
- 西野
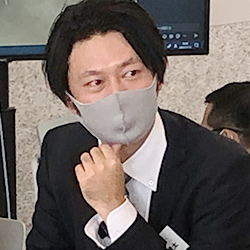
- 大阪は、個性が豊かで、地域色が強いと個人的に思っています。私は大阪のやり方が正しいと思って今までやってきていますので、一度、客観的な目で大阪のやり方を見て欲しいと思っています。
- 松原

- 機電系は建築系に比べると人数が少なく良くまとまっていて、他部門に比べると東西交流も多いと思っています。せっかくそういう環境で仕事をしているのに、東西でいいとこどりをせずに、東西別々のやり方をするのはもったいないと思います。東西の良いところはもっと標準化していくべきだと思います。
- 櫻井
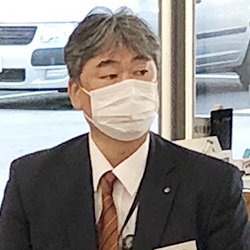
- 横田さんが東京へ行って、分電盤を統一したのは標準化の良い事例ですね。
- 豊田
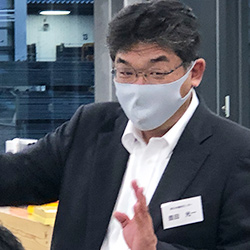
- 東西を分けずに全国規模で仕事をする方が効率的だと思います。西が忙しかったら東から来てそこで仕事をするように、東西関係なしに異動ができたら良いと思います。そのためには、タワークレーンや分電盤の仕様を統一することも必要です。これから人が少なくなる中で、人の動き方を変えていかなければならないと思います。
- 永田

- 安全の話に戻りますが、機材センターに技術の伝承が求められている基礎工事において、安全確保や公衆災害絶無を達成するためには、どのような体制や方法が必要と考えますか?
- 嵯峨

- 緊張感のある現場というのはメリハリが大事で、長い付き合いの会社とかメンバーとかありますが、ときに強く厳しく言うとか、レッドカード制をやるとか、そのぐらいの強い意識が必要で、それが思いやりではないかと最近思うようになりました。
- 赤尾

- 建築系の施工担当者は機械に関する知識が不足しているので、機械関連の災害を防止するためには機電担当者の力が必要だと思いますので、作業所でそのノウハウを伝授して欲しいです。
- 中江

- 杭工事を機材センターで見てもらったときに、ある2次会社の評判が悪いという情報を教えてもらい、1次会社と話をしてこの2次会社を使うのをやめて、施工体制を改善することができました。建築担当者はそこまで目が行き届かないので、こういった情報を機材センターから発信してもらえると安全・品質の確保につながっていくと思います。
- 西野
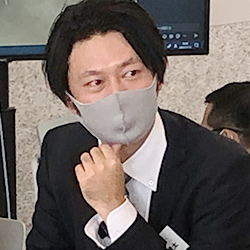
- コストや時間を度外視した意見ですが、原子力発電所の工事のように安全管理責任者として能力が高い人を配置すれば良いと思います。ただ、安全監視をするだけではなく、もし事故が起こっても再発防止対策をとことん検討したり、安全に対して妥協を許さない厳格な態度で現場員や作業員に接すれば、みんなの安全意識は変わってくると思います。
- 熊谷
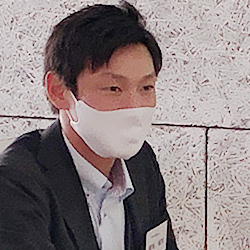
- 仮設電気の点検などで作業所に行くときに、基礎工事の施工管理をしている機材センターの方によく会いますが、結構現場は綺麗で安全や公衆災害にも配慮していると感じます。事故があった現場も適切に対処できていますので、今の体制には問題がないと思います。今後、新しく入って来る協力会社や当社の施工管理担当者に対する教育をしっかり行っていけば良いのではないかと思います。今、建築系社員への基礎工事に関する教育は行われているのでしょうか?
- 赤尾

- 技術部内で基礎工事の勉強会はやっていますが、作業所員を対象とした勉強会はやっていないですね。
- 豊田
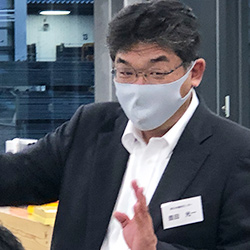
- 東京では、作業所から要請があれば、出前で基礎工事の勉強会を開いています。TSP合成壁って何っていうところから入って、SMWと紐づけて、品質管理と安全管理に必要な知識などを勉強会で教えています。
- 永田

- 基礎工事のエキスパートになるためには、地中の見えないところの品質確保が大事だと思いますが、どのような経験や知識があれば良いと思いますか?
- 嵯峨

- 私は失敗事例をもっと共有して欲しいです。最近は、失敗事例を報告書にまとめたり、現場ごとにシートを作って失敗事例も含めて結果を残すようにしています。昔はそこまでやっていなくて、周知できずに忘れ去られていってしまう事も多かったのではないかと思います。これからは失敗事例をオープンする風土づくりが大切だと思います。
- 紅屋
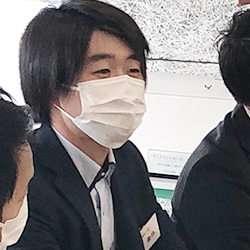
- 私は経験がないので良くわかりませんが、地中までカメラを下して見るか、潜って見に行けば良いのではないかと単純に思いました。
- 竹内

- 連壁をやっている時に鉄筋籠を落として、どうしようかとなって、その時に潜ってみようかという話になったんですけど、潜っても中は見えないよねとなって止めました。
- 豊田
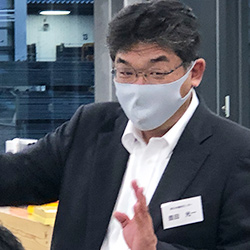
- そういう意味では、東京は結構潜水工を呼んでいます。拡底機を杭穴に落として、もうどうしようもないので潜水工を呼びました。まず、最初は自力で上げようとして、無理な場合は潜水工を呼んで上げてもらいます。それでもダメな場合は、最終的にはCD掘削機で壊して上げます。
- 赤尾

- 先程の失敗事例の話もそうなのですが、工法の特徴や癖だとか、こういう所が失敗しやすいといったようなことを、まだ現役のベテラン社員の方から聞き出して、みんなで共有できるようにしていくと良いですね。
- 永田

- 時間的に最後の話題になりそうですが、1990年代後半まで実施していた直営施工のメリット・デメリットや、技術の伝承をどのように考えるか、皆さんの考えを聞かせてください。
- 豊田
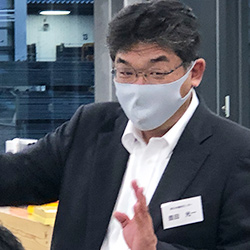
- 直営施工についてよく分からない方もいると思うので補足しますが、機械センターが基礎工事用機械を持って、社員が実際に杭・山留工事を施工することです。早く言えば、一次下請会社のような感じで、お金を含めて一式請負で施工することです。
- 中江

- メリットは、安全・品質管理レベルが高く、ブランド力もあり、お客様から信頼されることだと思います。デメリットは、自分たちで機械を持つのでランニングコストが掛かることだと思います。
- 山添

- メリットは、外部流出費用が抑えられることだと思います。デメリットは、人員確保が困難なことだと思います。技術の伝承については、先程話があったように、失敗事例を共有して、そこから学ぶことを継続していくことが大事だと思います。
- 熊谷
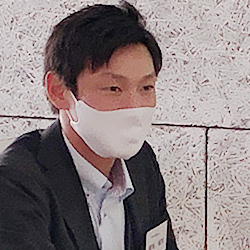
- 現在の機材センターにおける基礎工事体制の礎になったと思います。作業所長アンケートからも分かるように、基礎工事は評価されていますので、直営施工はその流れを作ったと思います。デメリットは、建築担当者の基礎工事管理能力が低下していることだと思います。
- 鈴木

- 私が名古屋にいた時、PC工事を機材センターが直営施工をすることで、契約調達単価を3割近く低減できたことがありました。直営施工で協力会社を牽制して、専門工事会社にチャンピオンシップを握らせないということも、先輩方はやられていたんですね。
- 永田

- まだまだ話題はつきませんが、皆さんから活発なご意見をいただき、あっという間に時間が過ぎてしまいました。大変残念ですが、時間になりましたので座談会はここで終了させていただきます。皆さん、ご協力ありがとうございました。長時間お疲れ様でした。
おわりに
- 洗

- 皆様半日ご苦労様でした。
今朝私は名古屋市内で地下鉄に乗って来たのですが、名古屋地下鉄も100周年らしいです。調べてみるといろんな会社や団体が100周年を迎えていて、ほぼ100年前に日本の近代化が始まったということで、その中の一つに我々の機材センターにも当てはまるようです。
今日話をしていただいた皆様方のいろいろな意見の中で、製和会活動に関しては、東日本と西日本で若い所員の意識に差があり、また製和会の役割やあり方も違うということも判りました。
また、人材交流をしていきたいという話がありましたが、これはやっていった方がいいと思います。人事制度上、今のままでは支店間異動は難しいですが、できる範囲でやっていきたいと思います。
50年後100年後の建設機械という話題では、皆さんからいろいろな面白い話を聞かせていただきました。私は今回の企画段階から10年後ではなく、50年後100年後のほうが面白い話ができるのではないかと思っていました。私はかつて外部団体のワーキングで「2050年の建設機械」を想像してレポートにまとめたことがあります。その中では、先ほどの話にもあったようにドローンのような揚重機械や、巨大なテーブル型の機械が道路を走ってきて、所定の場所で柱や壁を展開してそのままビルになるというのや、揚重機として、今のクレーンのようにワイヤーで吊り上げるのではなく、モノを下から投げて、それを上で受け止めるという新しいクレーンを提案し、非常に楽しかったことを記憶しています。今回の座談会のテーマの2030年というと、近すぎて現状の延長でのアイデアになってしまってあまり突飛なアイデアが出てこないのではないでしょうか。アイデアや発言に対する責任のないようなところで未来の話を考えてみるというのも面白いと思います。現状にとらわれず、考え方を多様化し、視点を広げていくということは、今後の業務にもつなげられるのではないかと思います。
昨日は年代が少し上の人たちの話を聞かせてもらいましたが、同じテーマなのに思っていることが違うということを感じました。また、今回のような機会が持てることを楽しみにしています。
半日ありがとうございました。
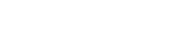 建設機械
建設機械