座談会2日目(年代:20~30代)

「機材センターが2030年に目指す姿」
- 永田

- 当社では、タワークレーンや工事用エレベータ、キュービクルなどの機械を保有しています。タワークレーンや工事用エレベータなどに関するコスト低減について、実施事例や実施して欲しいことについて聞かせてください。
- 紅屋
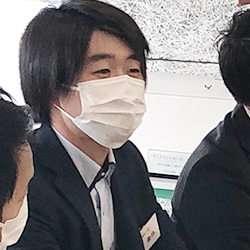
- タワークレーン・工事用エレベータとも、効率的に荷揚げや運搬ができるような計画を細かく決めて工程を組むことがコスト低減になると思います。また、様々な揚重物を各会社で揚重すると人手や時間がかかるので、例えば、揚重作業はすべて鳶さんが行うようにできれば、コスト低減になって安全性も向上すると思います。
- 熊谷
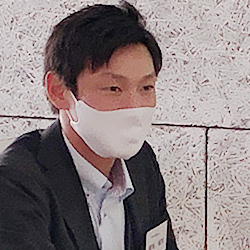
- エレベータ着床階の床先やシャフトの開口養生を効率化することがコスト低減につながると思います。機材センター内の開発改善で床先を無溶接でやる発表を聞いて、素晴らしい考え方だと思いました。あと、エレベータ開口に小梁を入れて幅300mm程度の開口を作り、そこにコンクリート配管を通している作業所があり、ちょっとした気遣いですが、良いアイデアだと思いました。
- 西野
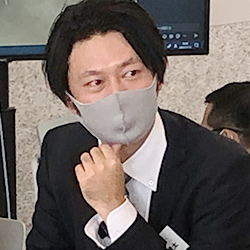
- 私は、できるだけ無駄が出ないようにタワークレーンの基礎や控えの計画をしています。アクティオは控え材の端部だけを自社で保有して、中央部は現場合わせで製作していると聞きました。ある程度どの機種にも対応できる仮設受梁や控え材を保有することができればコスト低減につながると思います。
- 山添

- 仮設電気の施工計画をしていた時に、工事期間が1年未満の作業所に対して、準備工事からキュービクルを設置して、電力会社との契約を1年以上にすることで基本使用料を低く抑えてランニングコストを低減したことがあります。
- 嵯峨

- 昔からクレーンの合図を無線でしていますが、無線に変わるものは何かないのでしょうか。協力会社間で無線のやり取りが出る場合があり、無線がないからクレーンが使えないと時間のロスが出てきます。例えば、個人のスマホが使えれば、無駄な時間が減って、無線設備にかかるコストも低減できると思います。
- 松原

- 技研で実験する時に、Teams会議の要領でスマホのカメラで実験の様子を映して、皆でbluetoothイヤホンを付けて、映像と音声を確認しながら進めていました。今のクレーンの無線合図は音声だけで通話できる人数にも制限がありますので、これからはスマホやbluetoothイヤホンが使えるようになっていくと思います。
- 永田

- それでは、機材センターの主要機械であるタワークレーンや工事用エレベータについて、揚重運搬効率を更に高めるためのアイデアを聞かせてください。
- 紅屋
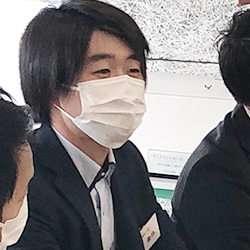
- 工事用エレベータでいうと、ハード面は、本設エレベータのように自動で呼び出して、扉を自動で開けることができれば、操作する時間が減って、効率が上がると思います。ソフト面は、現状できる簡単な方法としては、段取りを細かく組んで効率良く運搬することだと思います。
最近、東日本機材センターで購入した工事用エレベータ(HCE-3000HS)は、従来機より扉の開閉速度が速く、昇降スピードも速くなりました。機械の購入時にメーカと協議して性能を向上させていくことも大事なことだと思います。 - 中江

- タワークレーンの巻上速度を速くしたり、工事用エレベータの操作を簡単にしてオートメーション化すれば、揚重効率が向上すると思います。
- 赤尾

- タワークレーンや工事用エレベータは、安全面などの理由で今の揚重速度が最適なのだと思いますが、速度を上げるのに何か別の要因で支障をきたしているのであれば、そこ解決して速度を上げるのも一つの方法かと思います。
- 山添

- 中江さんが言われた工事用エレベータのオートメーション化は、今まさに開発グループで取り組もうとしている課題です。まずは遠隔操作に取り組み、最終的には自動化を目指すステップで開発を進めています。遠隔操作では、管制塔のようなところでエレベータや人の動きを見て、揚重工に指示を出すことで効率を上げることを考えています。
- 西野
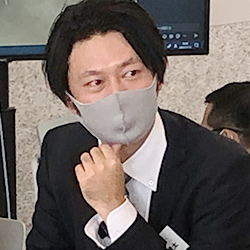
- 大阪の大規模現場では工事用エレベータに揚重工をつけることが多く、揚重工のスキルによって揚重効率が全然違ってくるという話をよく聞きます。呼ばれた階に行くだけの揚重工もいれば、どこの階に何が必要で、どの順番で回れば効率が良いかを考えながら運転する揚重工もいるそうです。今まで機材センターは揚重工に関して関与してきませんでしたが、これからは、効率の良い揚重運搬方法を把握して作業所に提案していくことも必要だと思います。
- 熊谷
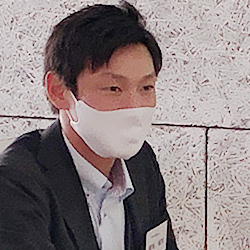
- 揚重工のノウハウをデータ化してシステムとして搭載することは可能になると思います。先程、紅屋さんから話がありましたが、新しく購入したエレベータは扉の開閉や昇降速度が速く、先日乗った時にその速さを体感しました。特に減速してから停止するまでの時間が速くて驚きました。但し、エレベータの扉の開閉については、未だに、内扉と外扉を別々に開閉する機構なので、本設エレベータのように同時に開閉できる扉を開発する必要があると思います。
- 松原

- クレーンやエレベータの能力には自重が含まれるので、ジュラルミン等の軽量パーツを採用することで揚重能力が向上すると思います。車は本体フレームに新しい素材を採用したり新しい技術を導入して燃費なども向上していますが、タワークレーンや工事用エレベータは車の進化に比べて全然進んでいません。もっとメーカが工夫をして、新しい材料や技術を導入すれば、揚重効率の高い機械が作れると思います。
- 永田

- それでは少し話題を変えて、機械を自社保有することによるコスト・安全・品質・供給などについてメリットとデメリットを伺っていきたいと思います。
- 松原

- メリットは、クレーンやエレベータに関する知見を社内に蓄積できることだと思います。機械を使うユーザー目線と貸し出す側の目線が同じなので、「TawaRemo」や「℃」などの新規開発が実施しやすい環境であることも大きいと思います。
- 紅屋
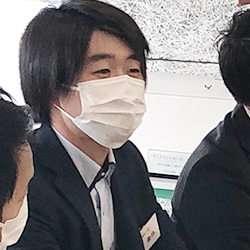
- 自社保有することで機械がいつもそばにあって実際に触れることができるので、機械についての知識・技能を深めることができると思います。機械の組立・解体においても、機械のことを深く知っていることで、より安全な指導ができると思います。
- 赤尾

- 自社保有による安全、品質面での安心感は高いのでメリットがあると感じています。逆にコスト面は、レンタル会社と比較してメリットがあるのか皆さんに伺いたいです。
- 西野
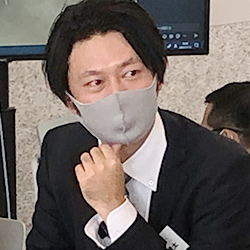
- コストに関しては、私の感覚ではレンタル会社から借りても作業所のコストは変わらないと思います。自社機械を使った方が社外流出費用を抑えることができるので、竹中工務店全体で考えるとコストメリットがあります。また、自社保有することで設計段階から入っていけますので、当社の施工物件に合致した機械を保有できることもメリットの一つです。
- 熊谷
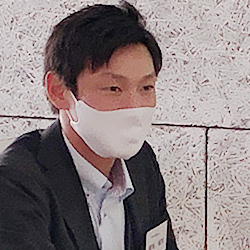
- 私は、松原さんの意見とほぼ同じで、メリットとしては建設機械に関する機械、制御、電気の知識・技術を持った人材を確保できることだと思います。自社保有せずに社外借用だけになると、メーカの技術者と直接話をする機会が少なくなって、技術力に深みが出てこなくなると思います。
- 永田

- それでは、今後、自社保有したいものや保有を見直すべきものについての考えを聞かせてください。
- 熊谷
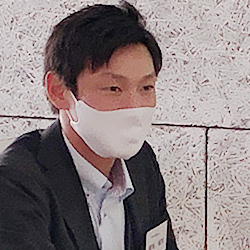
- 箱台車、コンクリートバケット、水タンク、沈砂槽などは法規制が特になく、安全・品質の確保のために機材センターが保有すべきものではないと思います。レンタル会社が保有していて供給能力が十分あるのであれば、ヤードも圧迫するので見直すならこの辺りの機械だと思います。
- 紅屋
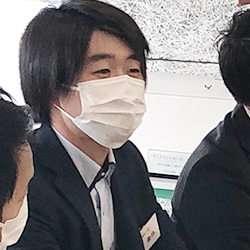
- タワークレーン・工事用エレベータにはいくつかのメーカがありますが、できる限り統一した方が良いと思います。これから人が少なくなって東西を行き来するようになっても同じ機械の方がやりやすいと思います。統一されている方が運用効率や整備品質も向上すると思います。使う作業員から見ても、竹中工務店の機械が統一されている方が扱いやすいと思います。
- 松原

- これからの機器の多くはインターネット回線に接続することが予想されるので、情報インフラ機器を保有してはどうかと思います。我々がクレーンやエレベータに詳しいのは保有しているからで、情報機器なども借りてきて使うだけでは知識は何も身につかないので、自社で保有して、我々が設置して通信の設定まですることで、知識が身についていろんな発想も出てくると思います。
- 中江

- 障害撤去工事は、工程が遅れることが多く、協力会社の能力によってかなり差があるので、自社で機械を持って施工することができれば、ある程度工程が読めて、安全や公衆災害防止の面でもメリットがあると思います。あと、改修工事で壁を壊すときに人力では時間がかかるので、遠隔操作の解体ロボットを自社保有できると、効率が上がり作業環境の改善にもつながると思います。
- 山添

- 保有機械のメーカは違っていても良いですが、それに関わる部品を共通化して欲しいと思います。例えば、タワークレーンのマストはどのメーカも同じ形状にできれば、運用効率が向上してコスト低減につながると思います。
- 西野
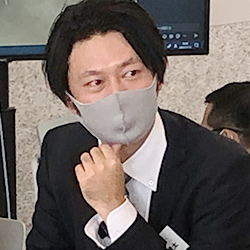
- 大林組で、北川鉄工所のタワークレーンに石川島のマストを使用していました。北川鉄工所の設計者に確認すると、強度的にも問題なくメーカとして保証しているとのことでした。当社で適用したことはないので、こうした考え方も視野に入れて、保有機械のあるべき姿を考えていきたいと思います。
- 嵯峨

- 技能の伝承を目的に機械を持つことは賛成です。より専門的な技術は手を動かさないと身につかないところがあり、昔直営施工をやっていた先輩方は、超マニアックな人が多く、我々はその領域に達することはおそらくできないと思います。そういう意味では近くに機械が有るのと無いのとではまったく違うと思います。
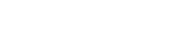 建設機械
建設機械