座談会2日目(年代:20~30代)

「機材センターが2030年に目指す姿」
- 永田

- 6月の横浜支店における吊り荷の落下による死亡災害や、7月の北海道支店における解体重機のバケット接触による死亡災害など、機械関連の災害が後を絶ちません。機械関連災害を防止するための、機械や装置のアイデアなどについて皆さんで語り合っていただきます。
- 松原

- 我々は、常日頃から事故をなくそうという意識で安全管理に努め、それを何十年と積み重ねている中で、今から劇的に事故をなくすためのハード的な改良を加えることは難しいと思っています。事故をなくすアイデアとしては、AIで安全な作業手順を学習して、不安全行動をすると指摘する「AI指導員」のような仕組みを構築できれば良いのではないかと考えています。
- 西野
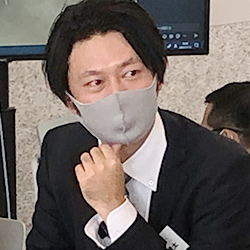
- 一人一人が注意するのは当たり前のことで、その当たり前のことができていなくて事故が起こっていると思っています。事故を減らしていくためには、危険個所に人が近づくとアラームで注意喚起するような、ソフト面での仕組みを強化していくべきだと思います。
- 紅屋
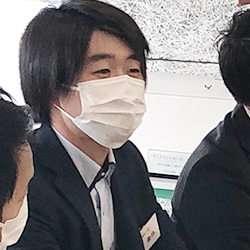
- 最近、玉掛け関連の事故が繰り返し発生しています。例えば、クレーンは玉掛けをするという概念をなくして、玉掛けをしないで掴むようなイメージで荷が落ちない機構に変えていければ、吊り荷が落ちるリスクは減ると思います。でも、やはり人の意識が大事なので、機械で変えていくのは難しいと思います。
- 赤尾

- 作業所の立場からすると、ヒューマンエラーが起きても事故を防止できるように、機械側でも対策できれば良いなと思っています。例えば、AIカメラで荷姿を認識して、不安全な玉掛けをしていればアラートが出て吊れないようにするなど、作業員に頼らないバカよけの技術開発に取り組んで欲しいと思います。
- 中江

- 調達的な目線でいうと、せっかく良い安全装置があってもコストがかかることが理由で使わないのはもったいないと思います。良いものは汎用的に使えるようにすべての機械に装備することができれば、ハード面での安全対策も普及していくと思います。
また、人が使うものなので、人がルールをしっかり守らないと意味がないものになると思います。やはりハードとソフトの両面で改善していかないと事故は減っていかないと思います。 - 熊谷
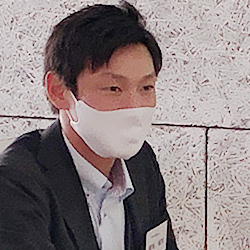
- ソフト面では、やる人の意識は非常に大事だと思います。ハード面では、かなり難易度は高いですが、紅屋さんが言われたように、玉掛けの事故をなくすために専用の吊り治具を作るのは良いアイデアだと思います。玉掛けのやり方が分からない状況をなくすために、そのやり方でしか玉掛けできないように限定させてしまうと事故防止につながると思います。
- 山添

- 私は、今まで人や機械を補助するという考え方でいろいろな技術開発に取り組んできましたが、熊谷さんが言われたように、これでないと何もできないように、制限を設けてやっていくという考え方は発想としてなかったので大変勉強になりました。
- 永田

- ここからは、協力会社に対する指導・教育についての考えを語り合っていきたいと思います。2018年に東北支店で「非製和会」協力会社によるクローラクレーン解体作業において死亡災害が発生し、今年も名古屋支店で同種の災害が発生しています。「製和会」と「非製和会」による安全対策の違いや、重機災害を繰り返さないための方策について皆さんの考えを聞かせてください。
- 赤尾

- 私は、竹和会と非竹和会は分かりますが、製和会と非製和会はあまり区別がつきません。作業所に非竹和会の協力会社が入って来たときは、当社のルールを指導するように意識しています。
- 中江

- 竹和会と非竹和会は、一応名簿がありますのでそれを見れば区別がつきます。私は調達部にいるのに、どの会社が製和会か認識できていなくて、製和会の名簿も持っていません。基礎工事会社については、どの会社が製和会か豊田さんから聞いて分かるレベルです。
- 嵯峨

- 製和会と竹和会のいずれも、会員か非会員による安全対策の違いはないと感じています。また、機材センターの中にいても、製和会の活動がよく分かっていないので、もっとPRして欲しいと思います。
- 紅屋
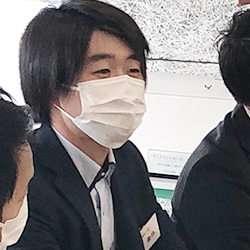
- 私も正直言って、あまり製和会の仕組みがよく分かっていません。同年代の人に聞いても同じように思っていて、機材センターのホームページで製和会が載っているところを見て、こんな感じかなと思った程度です。
- 松原

- 私は、製和会か非製和会かは、パッと見て分かります。作業所にいてもそうですが、製和会の方は事務所に入ってくる頻度が高くて我々と密に連携している印象です。
- 西野
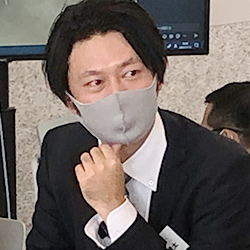
- 何年か前に、竹和会と製和会が合同で機械展示会をやりましたが、そうしたイベントを建築の人を巻き込んで定期的に開催すれば、製和会の活動をもっと広く知ってもらえると思います。
- 嵯峨

- 私は大阪で仕事をしていたとき、製和会のメンバーが機材センターに月1回くらい集まっていて、全然仕事で絡んでいない人とも名刺交換をしましたが、それがすごく新鮮でした。また、製和会パトロールに若手を連れて行くのも勉強になるので良いことだと思いました。
- 西野
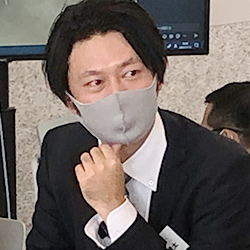
- 竹和会は「ユース」という次世代の若手を中心とした会があります。製和会は結構メンバーが固定されていますが、ユースのように事業主の次世代や3世代が集まって、新しい意見を取り入れていけば、もっと変わっていくのではないかと思います。
- 赤尾

- 竹和会ユースは、若手の作業所員も接しやすいメンバーが多くいるので、お互いに本音の意見も言いやすく、協力会社のことを深く知るきっかけにもなるので、すごく良い会だと思います。
- 永田

- 竹和会や製和会に対する皆さんの想いが良くわかりました。非製和会が重機災害を起こさないために何をすれば良いか、もう少し皆さんの意見を聞いていきたいと思います。
- 山添

- 製和会とか非製和会とかは関係なくて、協力会社の事業主の意識が大事だと思います。私は、製和会と非製和会との安全に関する違いが良く分かっていないので教えて欲しいです。
- 岡崎

- 機械事故があると、まず製和会に入っている会社に速報メールで事故情報を共有します。もちろん、2ヶ月に1回の定例会で集まったときにも伝えますが、非製和会はメーリングリストに入っていないので、事故情報が共有されないのが大きな違いで、非製和会への情報共有が課題でもあります。
- 嵯峨

- 非製和会は、送り出し教育がまともにできていないので、新規入場者教育のときに当社の現場を知ることになると思います。そこで「竹中の現場」だという強い意識を持たせて、安全意識を高めていくことが大事だと思います。
- 中江

- 事故があったクレーンの解体工事でも、作業手順書は作るわけで、その通りにやっていないので事故が発生していると思います。製和会は事故情報を共有しているとのことですが、そもそも作業手順書をしっかり守っていれば、事故は起きないのではないかと思います。
やっぱり協力会社の職長や当社の作業所員が作業手順書の内容を確認して、それを作業員に理解させることが重要です。当社の作業所員や機材センター所員が、それをしっかり現地で見ながら「何かおかしくないか」としっかり声掛けができれば、今回のような事故は起きないと思います。 - 紅屋
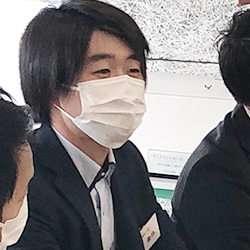
- 東北の事故もそうですが、ただでさえ危ない作業をしている中で、事前打合せで決めた内容から、作業時間が短くなるとか、作業場所が狭くなるといったようなことが起きると、作業員のゆとりがなくなってきますので、心の余裕を持たせるような環境づくりが大事だと思います。
- 松原

- 地方の作業所でクローラクレーンなどの組立・解体があるときは、危険作業事前打合せにテレワークで機材センターや製和会が出席して、非製和会のクレーン会社に危険なポイントや事故事例を説明すると、そこに注意して作業してくれるのではないかと思います。
- 西野
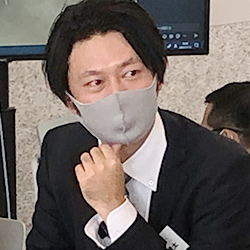
- 我々ができることは、例えば、クローラクレーンの組立・解体が5日かかるものを、3日でやるように作業所長から言われたときに、我々が盾になってクレーン会社のリスクを摘み取ることだと思います。計画段階から安全を意識した計画をすることは非常に大事なことで、そこは我々がしっかり守っていくべきところだと思います。
- 中江

- 東京と大阪は機材センターでクローラクレーンのコストを決めていますが、名古屋は調達部が何社かに見積もりを徴収して、安いところに発注しています。東京と大阪は、安全設備を見込んだ上で、金額を決めていると思いますが、名古屋のように競合させると、協力会社ごとの判断になり、必要な人数を減らして事故が起こってしまう可能性はあると思います。
- 豊田
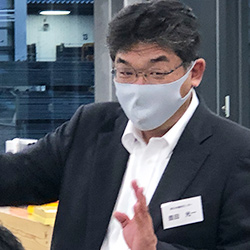
- 製和会の会員会社は横のつながりがあって、例えばA社で、クローラ解体で事故を起こしたときに、B社で過去に起こった同種の事故の対策を情報共有することができます。そうしたことで全体的に安全レベルの底上げができるのが製和会の強みです。
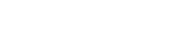 建設機械
建設機械