座談会2日目(年代:20~30代)

「機材センターが2030年に目指す姿」
- 永田

- 抜本的な生産性向上と働き方改革が当社の喫緊の課題です。作業員不足や4週8閉所などによる稼働日数の減少に対応していくためには、更なる機械化・ロボット化や大型ユニット化等による省力化工法などへの取り組みが求められますが、それらの実現に向けて注力すべき点やアイデアを聞かせてください。
- 山添

- ロボット化する上で完全な無人化は難しいと思います。専門知識がない作業員でも手順通り操作を行えば在来工法と同等の品質や時間で施工できるような機械化を目指しています。極論すると、その辺を歩いている人を連れてきて「ここのボタン押しといて」と言っても施工できるような単純化したロボットで対応していきたいと考えています。
- 西野
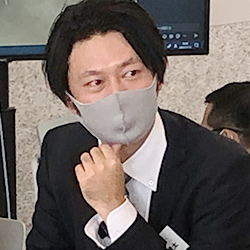
- 大阪は、どんな計測や墨出しでも測量工に依頼することが多く、夜間にロボットが親墨や基準レベルだけでも出すことができれば、総工数の削減やコスト低減に効果があり、働き方改革にもつながると思います。
- 松原

- ロボットを動かすためにネットワークインフラを確実に構築することと、今まで現場に足を運んで集めていた情報を、センサーやカメラを各所に設置して情報収集するだけでも労働生産性は向上すると思います。
- 紅屋
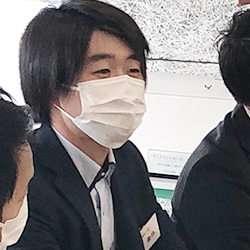
- 資機材を運ぶのには時間や手間がかかり、重労働でもあるので、漠然としたイメージですが、空港のベルトコンベアのような荷物を運搬する機械があれば良いと思います。何かを取付けたりするような細かい作業は、人間の感覚が必要なので無理に機械化する必要はないと思います。
- 中江

- 掘削工事における自動掘削機の更なる開発をして欲しいです。今あるGPS掘削機は、都内では通信が途切れて施工できない場合があるので改善して欲しいです。もっと言えば、図面さえあれば自動に掘削できるレベルを目指して欲しいと思います。
- 赤尾

- 色々な作業所長の話を聞くと私もそうですが、材料の搬入や移動などの揚重運搬作業を夜間に自動でやって欲しいというニーズが多いです。様々なハードルはあると思いますが、無理やりにでも実例を増やしていけば理想的な形が見えてくると思います。10年後にはそれが当たり前のようにできるようになって欲しいと思います。
- 熊谷
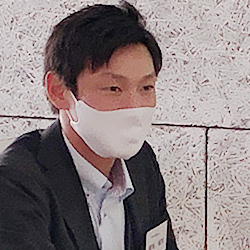
- 開発を行っていく上で、開発したものを使うための段取りとか管理するために労力を割いていたら、本質的な省人化にはならないと思います。段取りや管理などに時間や労力ができるだけかからないようにすることも大切だと思います。
- 永田

- 次に、ICT・情報化・デジタル化へ向けて機材センターの対応力を高めるために何が必要か皆さんの考えを聞いていきたいと思います。
- 松原

- 機材センターの開発担当者は通信インフラの知識が不足しています。機材センター内に専門の情報化グループを作り、そこで通信インフラの計画や構築業務を担っていくべきだと思います。東日本では熊谷さんが対応してくれていますが、本業ではないので、どうしても片手間になってしまい、知識を深める時間も取れず、苦労されていると思います。
- 熊谷
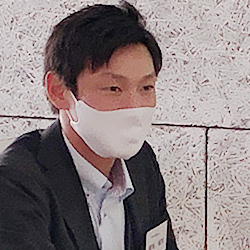
- ICT等の対応を機材センターでやっていくのであれば、特化した知識がないと難しい部分もあるので、対応体制を明確にして、専門知識を持った人を採用または育成して、新たなグループで対応していくべきだと思います。
- 赤尾

- ドコモなどと連携しているように他業種のメーカから我々とは根本的に違う考え方を取り入れることが必要だと思います。医療業界は他業種が参入する旨味が多くあるため投資がどんどん進んでいるイメージがありますが、建設業は儲からないイメージが障壁になって、他業種からの参入は難しいのかもしれません。
- 山添

- 西日本機材センターのアナログな部分の話ですが、日々の作業所との入出庫のやりとりは、ファックスとかメールで行っています。作業所が欲しい分電盤などの数量をスマホの専用アプリに入力すれば、直接DEPOTに反映して注文できるような簡単なシステムを構築して、作業所と機材センターとのやりとりにかかる手間を軽減したいと思っています。
- 西野
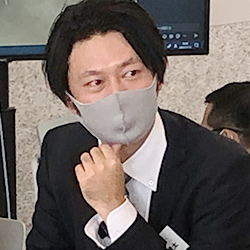
- 私は電気出身なのでTSUNAGATEなどもある程度は分かりますが、現業に追われて新たなことを勉強する時間がほとんど取れない状況です。作業所からこんな機械はないのと聞かれた時に即答できず、開発グループに確認してから返答するような対応で心苦しく思うことがありました。開発機械についても知識として持って、誰から何を聞かれても素早い対応ができるようになりたいと思います。
- 永田

- 少し毛色が変わった話題になりますが、50~100年後に実現したらいいなと思う基礎工事用機械についてアイデアがあれば聞かせてください。超高層建物の解体など、基礎工事以外のアイデアでも結構です。
- 中江

- 無人掘削機を実現して欲しいですね。あと、超高層解体における重機を軽量化して床補強を減らしたり、アタッチメントを改良して更に厚い壁を噛めるようにして欲しいです。超高層解体はハットダウンなどいろいろな工法がありますが、竹中工務店としてコストが安くて生産性の良い解体工法を確立する必要があると思います。
- 赤尾

- 全工種で作業員が少なくなっていくと思いますので、夜間に自動で動いてくれる様々なロボットが実現して欲しいですね。
- 松原

- 解体工事でブロック解体したいと思っても、タワークレーンを設置するのはハードルが高いので、バックホウを載せるぐらいの感覚で、吊り切りと圧砕を1台でまかなえるような自己完結型の解体重機を実現したいです。
- 西野
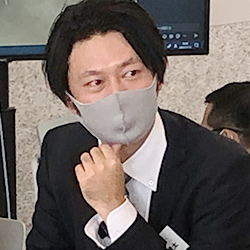
- 山留工事は、図面があれば位置出しの自動計測ではじまり、自動で掘削して、芯材建て込みからセメントミルク注入まですべて自動でできて、杭工事も同様に、鉄筋籠を自動で製作して、孔壁測定から建て込みまですべて自動でできれば理想的だと思います。
- 嵯峨

- 例えば、同一作業所で山留工事から既成杭工事へ移行する場合に、同じ3点式杭打機を使うのに協力会社が変わり、機械も入れ替えるケースがありますが、若干の装備が違うだけなので同じ機械を使って1社でできるのではないかと思っています。3点式杭打機で、障害撤去、地盤改良、山留、構台杭、既成杭まですべて1台で施工できる機械の多機能化と作業員の多能工化ができれば面白いと思います。
- 熊谷
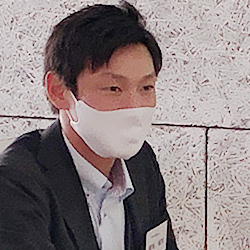
- 喫緊の課題となっているカーボンニュートラルの話ですが、水素燃料で動く車は世の中に出てきていますが、建設機械に適用されていくのは、もう少し先になると思います。まだイメージは湧きませんがインフラの整備を含め脱炭素への取り組みは考えていく必要があると思います。
あと100年後は、もうタワークレーンの時代ではなくて、ハイパワードローンとかで、大型ユニット化した部材をつけているようになっていたら面白いなと思います。 - 松原

- 私は100年後には、3Dプリンターですべての建物が建つ時代がくると思っています。
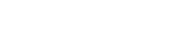 建設機械
建設機械