座談会1日目(年代:40~50代)

「機材センターが2030年に目指す姿」
- 鈴木

- 大型プロジェクトなどでは、機電系社員が作業所に配置されることがあり多くの評価を得ています。基礎工事など工事限定での常駐対応を含めて、今後どの分野での施工管理が求められるのか、皆さんの考えを聞かせてください。
- 中島

- 現在、機材センターが実践されている地盤・基礎工事と特殊工事分野は現状通り、優先順位を高めていくべきだと思います。機材センターのマンパワーは限られていると思いますので、工事の職域を広げるよりも、今やっていることをきっちりやって進化・発展させていくことが大切だと思います。
- 嘉本
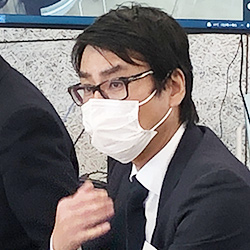
- 役員や部門長にインタビューをしたときに、基礎工事で機材センターが支援してくれたことが印象に残っている方が多かったです。着工して直ぐの時は作業所員も少ないので、作業所がやるべき仕事も機材センターがやってくれている印象を持たれています。基礎工事で躓くと後々の工程に及ぼす影響も大きいので、機材センターに入ってもらって良いスタートが切れて助かったという声が多かったです。
やっぱり機械系社員は作業所に配属される機会が少ないので、作業所の施工管理業務を経験して知識の幅や視野が広がるという点でも、作業所の常駐支援はやっていくべきだと思います。 - 豊田

- 基礎工事に機材センターが常駐して支援することは大事ですが、そのための教育体系ができていないことが問題だと感じています。基礎工事で人を育てるには最低でも5年程度かかるのですが、今はその期間が取れなくて、作業所に行って覚えるしかなくて、支援と言いながら現場で勉強している、というのが現状です。教育体系を見直していかないと、常駐して欲しいという声が今はありますが、将来的に知識や経験の乏しい人が常駐して「お前何しに来たんだ」と言われてしまうのが一番怖いです。
- 竹内

- どのような教育体系があれば良いと思いますか。
- 豊田

- 一番手っ取り早いのは、機械を教育用に1台保有して、機械を触りながら身に染みて一連の工事を覚えるのが良いと思います。やっと一人前になったかなと思うと別のグループに異動してしまうことが多いので、ローテーションが早すぎることもあると思います。
- 鈴木

- 小林(良)さんは事前アンケートで改修工事について書かれていますが、どんな内容をイメージされていますか。
- 小林(良)
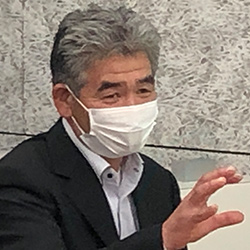
- これからは新築工事よりも改修工事が多くなっていくと思いました。塔屋の看板交換工事などで、屋上にクレーンを設置するときに、改修工事の担当者はほとんど機械の知識がないので、機材センターが常駐して機械も一緒に改修工事を施工管理して欲しいという話はあると思います。
- 小林(智)

- 私はダンパー取り付けなどの耐震工事を担当しましたが、ダンパーの取り付けだけでは作業所も受け入れてくれなくて、柱を触ってジャンカがあれば協力会社に連絡して補修したり、建築の仕事も一式で担当してやっていました。約5年間やっていましたので、柱を直したり梁を直したりするのが得意分野になりました(笑)。
- 小林(良)
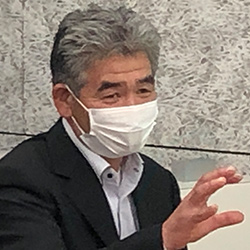
- たぶん作業所で色々な経験を積むことで応用力が身に付き、知識や技術の幅も広がると思います。
- 松岡
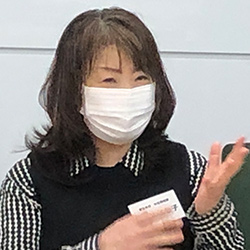
- 機材センターの方は仕事に取り組むプロセスの経験を積んでいると思うので、そういう意味でオールマイティーだと思います。安全環境部にも是非来て欲しいです(笑)。
- 鈴木

- 今、技術の伝承の話題に入ったところですが、皆さんから活発なご意見をいただき、あっという間に時間が過ぎてしまいました。大変残念ですが、時間になりましたので座談会はここで終了させていただきます。皆さん、ご協力ありがとうございました。
おわりに
- 洗
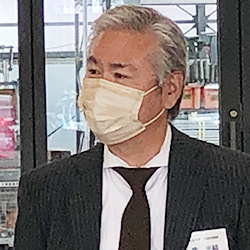
- 皆さん半日お疲れ様でした。
機材センター創設100周年を機会に、他部署の方々を含め、多くのご意見をいただきました。機材センターは、昔は機械の運転手、整備工として入ってこられた方々がいた部署から、役割を変えてきて、クレーンや杭打機の運転、今では機械施工計画や管理をしたりと変化しており、対応分野も基礎工事直営施工、特殊工事や免震化工事対応であったり、私がいたころはPC鋼線・鋼棒の緊張工事などもやっていました。100年を節目として、我々はどちらに向かって進むのかということを考える貴重な一助になったと思います。別のワーキングで機材センターの将来を見据えた「あるべき姿」を考えていくことを計画していますのでそこでの活動に生かさせていただきます。
今回ご意見いただいた東西交流やローテーションは、人事制度上、今現在は少し難しいところもありますが、できる範囲で検討していきたいと思います。機械系に限らず建築系社員でも東西経験を推奨されていますので、我々建設機械系も積極的にやらなくてはいけないと思っています。
すべてのテーマについて意見を聞けなくて、申し訳なく、消化不良的なところはありますが、貴重なご意見ありがとうございました。
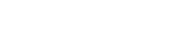 建設機械
建設機械