座談会1日目(年代:40~50代)

「機材センターが2030年に目指す姿」
- 竹内

- 当社では、タワークレーンや工事用エレベータ、キュービクルなどの機械を保有しています。タワークレーンや工事用エレベータなどに関するコスト低減について、実施事例や実施して欲しいことについて聞かせてください。
- 田中

- タワークレーンの基礎に使用する仮設受梁の転用に取り組んでいます。ただし、数年置いていると錆が出て、機材センターとしてはケレンや塗装の費用が掛かかってしまいますが、竹中工務店全体で見るとコスト低減できています。
- 小林(智)

- 私はタワークレーンの計画段階で転用できる仮設受梁がないか確認しています。そのまま使えなくても、加工して使えるものは有効活用するようにしています。仮設受梁の寸法などをリスト化して、要不要の判断が早くできるようにしています。
- 小林(良)
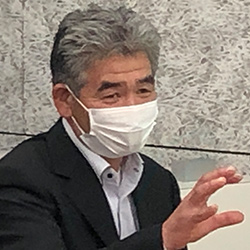
- 故障やトラブルが少なくて扱いやすい機械を購入することがコスト低減につながると思います。最近購入したタワークレーン(JCL-530)は故障が少なく、組立解体もやりやすくなりました。
- 嘉本
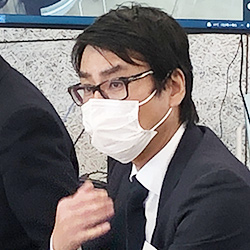
- 新しい機械はメーカーも工夫しているところがあり、不具合も少なく、運搬台数や組立解体工数も昔の機械に比べるとだいぶ減っています。そうした点はコツコツと作業所の原価低減につながっていると思います。
- 中島

- 竹中工務店全体で機械を効率よく使うにあたり、設計施工の会社ですから、例えば、工事用エレベータの最適な設置場所をプロジェクトの初期段階で意匠設計者や構造設計者と事前調整ができます。ここを変えれば工事用エレベータを効率的に稼働できるとか、後々のダメ部分を少なくできて効率的に工事を進めることが可能になるなど、大きな効果につながると思います。
現在、竹中新生産システムではフロントローディングをして、後戻りのないものづくりに取り組んでいますので、機材センターの方々からも専門家としての意見を川上で出して頂けると、より良いものづくりにつながり、コスト低減にも寄与すると思います。 - 嘉本
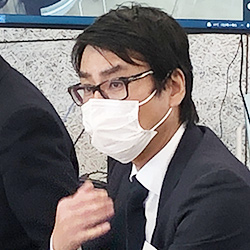
- 昔と比べるとだいぶ変わってきたと思います。技術部の計画と実施が全然違うことって私が若いころは結構あった印象があります。タワークレーンの計画が移動式クレーンに変わっていたり、その逆もあったりしましたが、最近は減ってきたと思います。
- 中島

- 昔は着工する前に作業所長が決定すると、クレーン配置や工事用エレベータ配置が変更となることがありました。しかし、今は早い段階から作業所長が決まって、作業所の生命線となるクレーンやエレベータの配置を決めていますので、内勤部門と作業所とが上手く協業でき始めていると思います。こうしたフロントローディングをより加速すれば、コスト低減にもつながる大きな活動になると思います。
- 洗
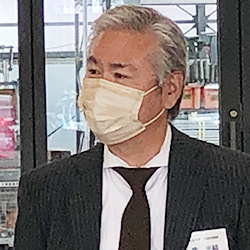
- 昔、東京の超高層の作業所で、技術部の計画はタワークレーン2台でしたが、作業所長が1台に変更したことがありました。見かけ上はコスト低減になったかもしれませんが、その分他のところにコストが掛かり苦労も多かったと記憶しています。やはり、早い段階から精度の高い計画をつくり込んでいくことがコスト低減につながると思います。
- 中島

- 作業所で判断する最終決定者が、きっちりブレなくプロジェクトを進めて行くことが大切だと思います。一方で、昔は主要部材を大きく変更しても、確認申請にそれ程時間がかからなかったのですが、今は少しの変更をするだけでも申請手続きに時間がかかります。そのためにも早い段階から精度の高い図面をつくり込んでいくことが重要だと思います。
- 嘉本
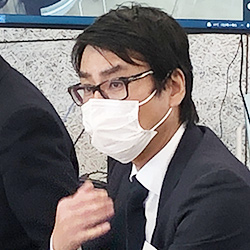
- それができるのは2フェーズか3フェーズの段階で、そこでいかに精度の高い計画がつくり込めるかだと思います。それって、かなりコスト低減につながっていると思いますが、中々それを金額で評価し難く、表に出てこないのが残念です。
- 中島

- 会社をあげてフロントローディングを取り組んでいますので、それに乗っかって機材センターのプレゼンスを高めていって欲しいです。
- 嘉本
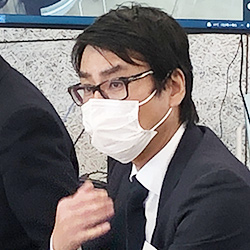
- これから4週8閉所の実現に向けて、人を減らした分を機械で補う計画になってくると思います。そうすると機械のコストは今よりも増えますが、機械を大型化して全体のコストが下がるのであれば、それはすごく意味があることなので、その辺を見極めていかないといけませんね。
- 松岡
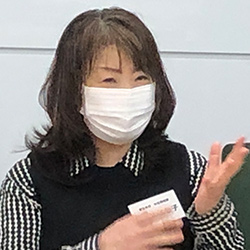
- 作業所のものづくりは、取り付ける場所に物を運ぶ運搬や揚重に、人やお金が結構かかっていて、作業所の負担になっていると思います。そういう部分を効率化するということは、良いものをつくってコストを抑えていくという意味で集中してやるべきところだと思います。
- 竹内

- 松岡さんより揚重運搬効率の話が出ましたが、タワークレーンや工事用エレベータによる揚重運搬効率を更に高めるために何が必要か、皆さんのアイデアを聞かせてください。
- 松岡
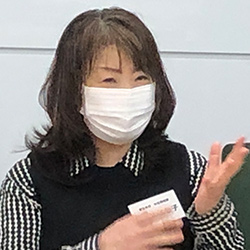
- 先程も言いましたが、物を取り付ける場所に運ぶことから建築は始まるので、夜のうちに機械が運んでくれて、ドラえもんの「どこでもドア」のように、朝行くとその場にすべて揃っていると、職人さん達にとっても働き方改革になりますよね。
- 中島

- ハード的側面で言えば、タワークレーンや工事用エレベータの稼働データを蓄積する技術ができてきていますので、データに基づいて何が最適かを分析することで効率化につながるヒントが得られると思います。また、昔のJCCのタワークレーンと今のVシリーズのタワークレーンとでは組立解体手間が大きく改善されており、機械自身の進歩も大きいと感じます。
ソフト的側面で言えば、先程も工事用エレベータの例で言ったように、ものづくりの生産性を川上で設計図書にスペックインしていくことが効率化につながってくると思います。 - 松岡
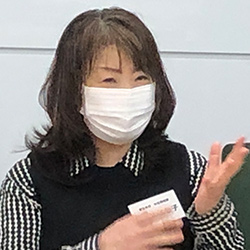
- 東京の集合住宅チームは、高層マンションが多いので、揚重回数というのはデータが蓄積・共有されています。ベルトスリングが使用できないと、揚重できる回数に影響が出てくると聞いて、なるほどなと思いました。ボードの先行揚重など、かなり緻密に揚重回数を積み上げてタクト工程を組んでいると感じました。
- 中島

- そういう意味でいうと、集合住宅は非常に効率よくつくられていますね。
- 竹内

- それでは少し話題を変えて、機械を自社保有することによるコスト・安全・品質・供給などについてメリットとデメリットを伺っていきたいと思います。
- 松岡
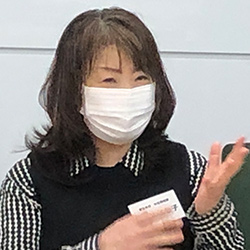
- 事務系の社員は、あまり機材センターの素晴らしさを実は良く分かっていなくて、機材センターの皆さんもシャイでアピールべたなところがあるので、もう少し社内でも分かるようにPRして欲しいと思います。皆さんが強み弱みをどのように思っているのか、逆に聞きたいなと思いました。
- 小林(良)
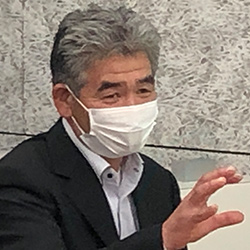
- 確かに、昔作業所に行くと「朝日機材さんですか」と言われたことがあって、機材センターの認知度が低いのかなと思った時期がありました。タワークレーンの組立解体で一生懸命泥まみれ油まみれになって仕事をしていると、社員じゃないという見方をされてきたことはあったかと思います。今はだいぶ機材センターは頼りになるなと思われるように変わってきています。
- 原田
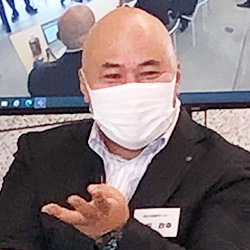
- PRべたっていうところは確かにあると思います。メリットは、自社保有しているとレンタル会社のコストを評価できる点だと思います。先日、作業所が直接レンタル会社に頼んだ無線機の単価よりも、機材センターを通した方がものの値段を知っているので安く調達できました。デメリットは、自社保有することで維持管理費がかかる点だと思います。
- 洗
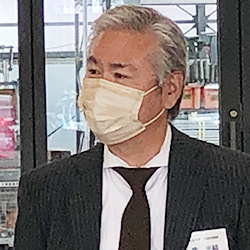
- 松岡さんが事前アンケートで機材センターが自社保有することでメリットが多いと感じている反面で、自社機械の組立解体で機材センターの指導員が怪我をすることを心配されています。そのことについて皆さんの意見を聞かせてください。
- 小林(良)
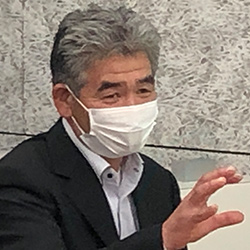
- 鳶さんより機材センターの方が機械に対する知識があり過ぎて、つい手を出してしまい、そこで怪我をすることがあると思います。たまに来て機械を触る程度の鳶さんには、機材センターの指導員が教えながらやっていますが、言葉で伝わらない部分を自分でやって示すことがあります。
- 松岡
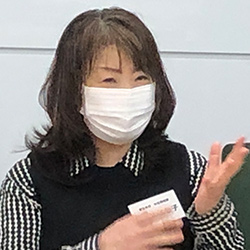
- 機材センターの災害は決してヒューマンエラーではないと思っています。鳶さんを含めた事前の作業手順の確認や周知が足りていなかったとか、いつもと違うやり方を具体的にせずに自分の頭の中だけにあったとか、若い指導員だったから予測ができなかったとか、そういう部分の能力を付けていかないと、きつい言い方ですけど指導もできないと思います。
- 板谷
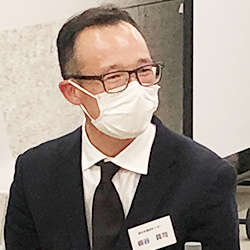
- 松岡さんの言葉が胸に沁みます。大阪の施工グループの仕事で怪我をしていないのは、どちらかというと管理側に入っていて、仕事で手を出すことが少なくなったのが要因だと思います。
- 田中

- 東京は怪我が多いのですが、指導員をやっているメンバーは若手社員が多くて、仕事を覚えて中堅になると他のグループに異動して、常に小林(良)さんが若手を教えているような状況で、指導員の人数が少ないことも怪我をしてしまう要因のひとつかと思います。
- 小林(良)
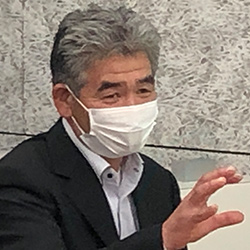
- 管理するには自分でやって経験しないと仕事の内容とか危なさを鳶さんや後輩に伝えていけないので、管理だけをやっていこうという中で、体で仕事を覚えるような経験というのも大事なのかと思います。
- 竹内

- 先日、大阪で指導員の合同研修をやって、協力会社の指導員が「管理だけで全く手を出さないことはできません」と言い切りました。小林(良)さんの意見と似ています。山本五十六の言葉にあるように、最初が「やってみせ」ですから、それがないと指導にはならないという考え方も確かにあるなと感じました。
- 櫻井

- 九州の場合は鳶工がほぼ1社で対応しているということもありますが、鳶さんから指導員は触らないでくれと言われるぐらい徹底されています。小林(良)さんの気持ちも分かりますが、身を挺して教えるのではなくて、もう少し根気よく言葉で教えていって欲しいと思います。
- 中島

- 私が経験したある作業所では「機材センターはものづくりのインフラを担う部署だ」と当時の作業所長に教わりました。一方で、先程話があったように、機材センターの方が泥だらけ油まみれになった姿を見て「あれがプロ集団だぞ」とも言われました。やはり、プロ集団が機械をメンテナンスしていることが品質であり信頼につながります。そこが自社保有のメリットだと思います。他の会社の機械が作業所に入って来るよりも、自社機械が入って来た時の気持ちは違います。自分のやる気というところにつながるように感じます。
あとデメリットでいうと、プロジェクトは景気にも左右されてプロジェクトの山谷が発生しますので、稼働率という点では難しい面があると思います。
そのためにもメリットとデメリットをバランスよく判断しながら、ただ単にコストだけに偏らないようにしていくことが大切だと思います。 - 小林(智)

- 私も自社機械が好きで、機材センターの自社機械は我々が提案した特許などが盛り込まれていますので、やっぱり鳶さんへの指導も熱くなってしまって、怪我も多少は出てくるんですかね(笑)
- 竹内

- 皆さんの自社機械に対する想いがよく伝わってきました。それではここで、今後、自社保有したいものや保有を見直すべきものについての考えを聞かせてください。
- 中島

- タワークレーンや工事用エレベータのような主要インフラを支える機械は自社保有していく流れを継承すべきだと考えます。一方で時代の流れに合わせて、いろいろな開発や先端技術が進んでいますので、新しい開発機械は、RXプロジェクトの中で上手く持ち合いながら調整していき、未来の建設業へ向けて発展させていく流れが良いと思います。
- 板谷
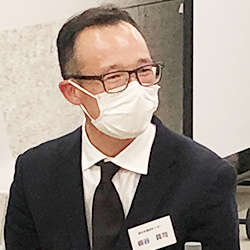
- 開発されてまもない機械は中島さんが言われたような持ち方をすれば良いと思います。汎用的に使用されるようになれば、レンタル会社や実際に施工する協力会社が保有すれば良いと思います。大阪でコンクリート均し機を保有していますが、作業所で故障などがあっても、機材センターが迅速に対応できない場合もあり、今後はレンタル会社などに展開していければ良いと考えます。
- 原田
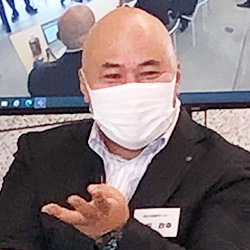
- 基礎工事用の機械を保有して、昔のように自分たちで乗るのではなく、基礎工事会社に貸し出してはどうかと思っています。やっぱり機械を持って触らないと、開発要素を盛り込むのが難しく、新しい機械に進化していかないと思います。
- 嘉本
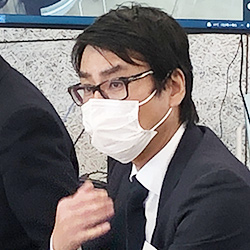
- 時代の流れの中で機材センターが保有するものは変わっていくと考えていて、最近のトレンドでいうと脱炭素という大きな流れがあります。例えば、水素を使って重機が作業所で動くという話になった時に、水素をどうやって供給するかという課題が出てきます。そうしたところに機材センターが関与していくことを求められたり、保有していくことも可能性としてはあると思います。
- 松岡
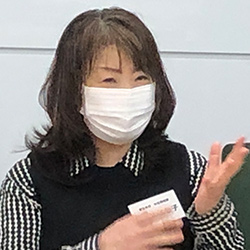
- 今の嘉本さんの話で、環境に配慮した機械というのは、何をおいても本当は今やっていかなければならない分野だと思います。入札の提案にしても二酸化炭素の排出低減は結構ポイントが大きいですからね。
- 嘉本
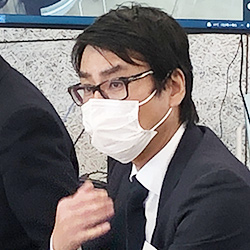
- 今までは使用電力のピークカットをするのに発電機を使ってコスト低減する計画を推奨していましたが、これからはコストだけでなく環境負荷も考えて計画しないといけなくなりますね。
- 田中

- ピークカットで言うと、東日本機材センターではキュービクルにIoTを導入していないので、ピークカットのピークが見えていない状況です。今後はキュービクルにIoTを導入して、複数の作業所の合算でピークカットができないかと将来的には思っています。
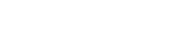 建設機械
建設機械