座談会1日目(年代:40~50代)

「機材センターが2030年に目指す姿」
- 竹内

- 6月の横浜支店における吊り荷の落下による死亡災害や、7月の北海道支店における解体重機のバケット接触による死亡災害など、機械関連の災害が後を絶ちません。機械関連災害を防止するための、機械や装置のアイデアなどについて皆さんで語り合っていただきます。
- 小林(智)

- 横浜での吊り荷の落下による死亡災害は、1t吊りの小さなクレーンのフックに4本のベルトスリングのアイを無理に掛けたために、フックからベルトスリングのアイが外れて吊り荷が落下してしまいました。もし、その下に人がいなければ重大災害は防げたわけで、人感センサーなどで吊り荷の下に人がいた時にオペレータに警報等で促す装置があれば良いなと思いました。
- 板谷
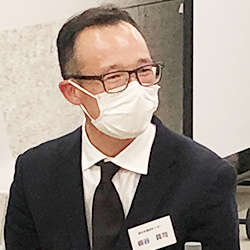
- 「AIスコープ」と言って、フックに取り付けたAIカメラが人を検知してオペレータにアラートで通知するシステムがあり作業所に導入され始めています。クレーンのフックから地上に立入禁止エリアを投影して作業員にも見える化する装置があれば、更に良いと感じています。
- 嘉本
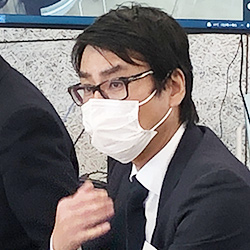
- 過去の機械災害は、機械や計画の不具合というよりも、その使用方法や手順に問題があったものが大半を占めます。機械は昔のものに比べると安全性は向上していますので、ハード面の開発というよりも、正しい使い方や手順で作業されているかどうかを監視して注意喚起するなどのソフト面の対策が求められるのではないでしょうか。先程の「AIスコープ」もそれに該当すると思います。
ただ一方で、あまりこれをやり過ぎると、リスク補償行動という言葉があるように、人間の感性が失われていきますので、装置の開発と教育とを合わせて取り組む必要があると思います。 - 田中

- 東京都内の作業所で、地上に円を描き、その中を立入禁止にして、垂直揚重はその中で必ず行っていて、とても良い案だと思いました。吊り荷の下に入るなというルールはみんな知っていたとしても、超高層では吊り荷が上に巻き上がってしまうと、そこが吊り荷の下なのかどうかも分かり難いところもあるので、円の中に人を入れないルールは良い案だと思いました。
重機バケットの方は、地下で円を描いても見えないので、プロジェクションマッピングのようなものを地上に投影して人払いをするのが効果的だと思います。 - 松岡
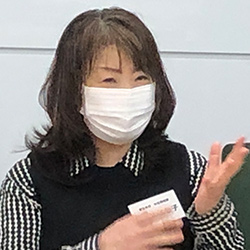
- いくら吊り荷の下を見える化しても、その範囲から玉掛者、作業者が退避する、退避させることの徹底が大きな課題です。今、東京の超高層の作業所で、一度吊り荷を横に水平移動させてから上にあげることにチャレンジしてもらっています。
重機バケットの災害については、人が入ったら照らす装置の開発をしていますが、入ってくる人が素人だと、照らされたとしても何なのかがわからないので、安全装置を開発する場合は、人の行動を知って開発をすることが大事だと思います。 - 嘉本
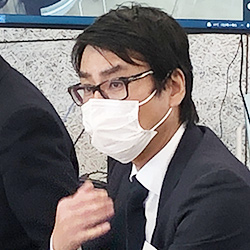
- 大阪の敷地一杯の作業所だと、荷取り揚重開口を作って、そこからしか物を上げないように自動的になりますので、それはそれで対策になっていると思います。揚重中そこに間違って入る人がいないように管理をする必要はあります。
- 小林(良)
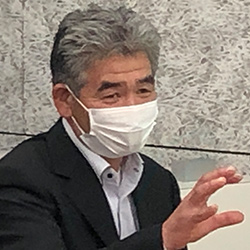
- でもそこが鳶さんの作業エリアだとすると、他の人は入らないですが、鳶さんは次の段取りで入ってしまいます。荷取りヤードにトラックがあると次の段取りをしてしまうので、荷を横に移動して誰もいないところで垂直揚重して、荷が上がりきるまで人払いをする必要があると思います。
- 鈴木

- 今日は答えを出す場ではないんですけど、鳶さん限定でエリア感知するなど、何か組み合わせると画期的な安全対策につながるのではないかと、いろいろと考えてしまいます。
- 原田
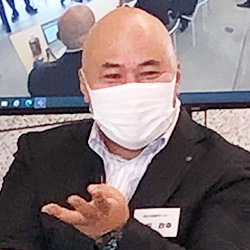
- 災害はどうしてもヒューマンエラーが起因することが多いので、起こった災害のエビデンスを残して、人間の行動をAIで分析することでリスクの見える化ができれば良いと思っています。
私は重大災害が発生した作業所を経験したことがあります。トラベリング工事で約30m上から墜落する事故があり、その原因はトップライトの踏み抜きでした。人がこんなところに入るのかという隙間しか空いていないんですよね。その災害の本当の原因は何だったのかというのが自分の中にあって、エビデンスが残せれば良いと思っています。 - 中島

- 皆さんの話と似通ってきますが、ハード的な側面ですと、先端技術は益々進化しますので、AIや危険感知などの技術を融合させることは非常に大事だと思います。
ただし、そういうものに頼りすぎると、車のナビを使うのと同じで、人は頭を使わなくなるので、身に付く度合いが薄くなります。そのため、先端技術はフェールセーフと捉え、あくまでもベースは人がしっかりと理解をして作業することが大切だと思います。
一方で、物事を自分の頭で理解することと、コミュニケーションを図って各作業の安全を確保するにはどうしなければいけないかということを日々積み重ねて実践していくことがベースになってくると思います。 - 嘉本
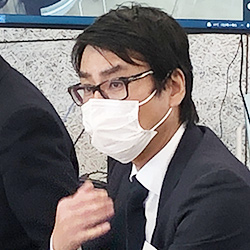
- AIによる災害分析の話が出ましたが、大阪ではクレーンにドライブレコーダーを付けていて、このデータが後々の災害分析に使えます。事故があったときの状況がどうだったのか当事者にヒアリングをしますが、カメラの映像と証言が違うこともあり、ドライブレコーダーに映っていれば一目瞭然です。災害の真の原因を見つけるという意味では、ドライブレコーダーやWebカメラなどのデータを上手く活用していくことも必要だと思います。
- 原田
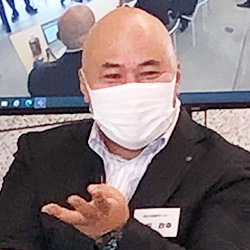
- エビデンスを残すためにカメラを設置するのですが、作業員の方は監視されていると思ってしまうので、うまく和らげる良い方法があればと思っています。名古屋サテライトにも360度カメラを付けていて、いつどこで誰が何をしていたか確認できます。監視が目的ではありませんが、監視されているから嫌だとの意見も出ています。
- 松岡
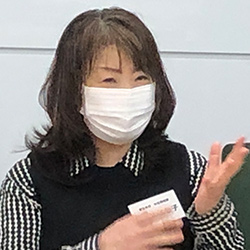
- 重機の接触防止や吊り荷の下を照らすセンサーなどの装置は結構コストが高いですよね。もっとシンプルでコストもかからないものがあるといいですね。普及すればコストも下がっていくと思うので、当社の全作業所で標準化できれば良いと思います。
あと、フェールセーフは結局バカよけで、絶対人がどうしてもそこに介在してものをつくる以上、人は間違えるので、そこで間違ったときのための対策をとるのが安全管理だと思います。やっぱり、人と機械をマネジメントするのが安全管理だと思いますので、機械だけを何か開発するのではなくて、両方を取り入れてマネジメントしていく考え方が大事だと思います。 - 竹内

- ここからは、協力会社に対する指導・教育についての考えを語り合っていきたいと思います。2018年に東北支店で「非製和会」協力会社によるクローラクレーン解体作業において死亡災害が発生し、今年も名古屋支店で同種の災害が発生しています。「製和会」と「非製和会」による安全対策の違いや、重機災害を繰り返さないための方策について皆さんの考えを聞かせてください。
- 田中

- 安全対策の違いについては、製和会として教育しているからというよりも、元々大きな会社で品質とか安全がしっかりした会社がそもそも製和会に入っていると認識しています。非製和会の事故については、製和会だったら防げたとも言い切れないと思います。もし、非製和会だったら事故が起きて、製和会だったら起きないのであれば、もっと製和会の活動を全店に水平展開して事故を起こさない環境を作っていく活動が必要だと思います。
- 嘉本
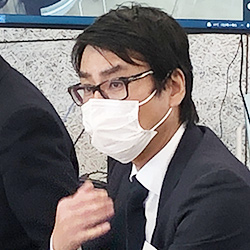
- 私も同じような感覚を持ったのですが、作業所を離れて10年以上経って当時の記憶があまり残っていないので、製和会と非製和会でそんなに違うのかどうか、皆さんの意見を聞いてみたいです。
- 豊田

- 製和会と非製和会の大きな違いは、例えば製和会に10社集まっているとすれば、1社が起こした事故の原因を製和会の10社で共有できる点だと思います。非製和会の会社はそれが共有できていません。
また、例えば「3分のワイヤー使用禁止」という暗黙のルールがありますが、製和会には浸透していて皆知っていますが、ちょっとした山留工事で入ってくるような非製和会の協力会社は、普通に3分のワイヤーを使っていることがあります。我々の常識ではあり得ないことをやってしまう、一番基本となるルールが徹底されていないのが非製和会に結構多いです。
また、一般的なルールを当社の作業所担当者が分かっていなくて、協力会社に指導することもできていない点も大きな課題だと感じています。 - 嘉本
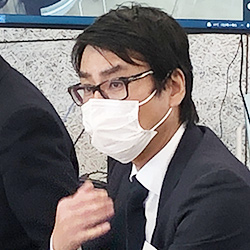
- 1次が製和会で2次3次が非製和会の場合、末端まで指導が行き届いているのか、皆さんの意見を聞かせてください。
- 櫻井

- 杭工事などは末端まで指導が行き届いていないことが多いですね。
- 豊田

- 基本的に1次会社が協力会社を集めて安全協議会などを月1回やっているはずで、そこでちゃんと指導してくれていると信じています。
- 岡崎

- 大阪では製和会と機材センターとの安全活動として、機械を持っている2次会社の整備工場を巡回したり、1次会社の安全協議会に2次会社の職長も参加しているところに出向いて安全教育をしたり、1次会社の番頭だけではなく、末端まで我々の想いが届くように心掛けて取り組んでいます。
- 中島

- 製和会、非製和会ということもあるのですが、そこで切り分けてしまうのではなくて、同じ作業所の中でやってもらう仲間なので、もし非製和会ができていなければそこをしっかりカバーしていくことが必要だと考えます。やはり製和会、非製和会で切り分けず、人と人とのコミュニケーションが大事で、ベースになると思います。
- 松岡
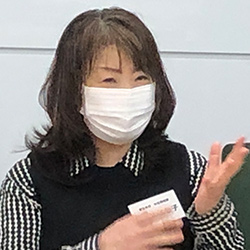
- 今、竹和会の訪問面談をやっていて、実際に作業しているのは2次3次会社の作業員がほとんどなのですが、1次会社がどれだけ我々が言っていることを2次3次会社に伝えているかどうかの差が、安全とかいろいろなところに現れてくるのは歴然としていて、そこを強化・育成していくしかないと思っています。
- 嘉本
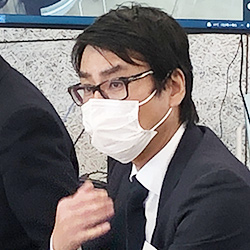
- 安全というのは妥協できないところなので、我々としても製和会だから任せっ放しにしないという意識は必要だと思います。当社が安全を守るという意識は絶対に忘れてはいけないし、2次3次といったところへの教育を実施していかなければならないと改めて思いました。
当社ルールや災害事例を共有するタイミングは危険作業事前打合せかと思いますが、そこには職長しか出ていないので、末端の作業員さんもいる場できちっと伝えることを地道にやっていくしかないのかなと思います。 - 小林(良)
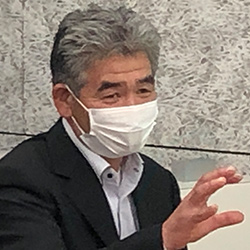
- 製和会に比べると非製和会は目が行き届き難いので、機材センターが作業に立ち会って確認するか、安全環境部と機材センターが協力して非製和会への安全教育や講習会などを行うことができれば良いと思います。
- 松岡
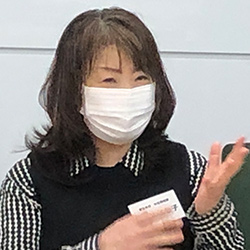
- 製和会と非製和会とでは災害で得た教訓を含めた情報量に絶対的な違いがありますよね。でもやってもらわなければいけないというときに、非製和会には情報が伝わってないことがすごく危険で、そこがリスクであることを我々が捉えて、事前に確認したり伝えたりといったプロセスを非製和会のときは入れるということになると思います。
- 豊田

- 非製和会が作業所に入る情報が機材センターに中々伝わってこないのも現状です。作業所長が好きな協力会社を調達部に紹介して、調達部が相見積もりをとって、そこに決まってしまうことがよくあって、その場合は機材センターや製和会に情報が中々入ってきません。
- 鈴木

- 基礎工事の場合は、どの班が来るか工事着手の2日前に決まることもあるし、1週間前に事前打合せした機械が段取りできずに、微妙に違う機械が搬入されることもありますよね。
- 松岡
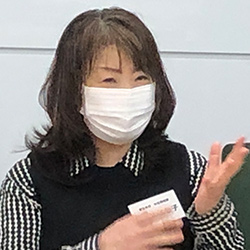
- 機械を入れた作業所が管理すれば良いのですが、うちの作業所の担当者は特に基礎工事の機械的なところは機材センターに頼っているので、管理のポイントを押さえて使っているのか疑問なところはあります。
機材センターが頼れる部署なので、頼っている分、逆に若い建築や設備の担当者の建設機械に関する知識が乏しくなっていくので、基礎工事の安全管理ポイントなどを見える化したり教えてあげると良いと思います。 - 豊田

- 最近、非製和会の事故が多いということで、調達部と連絡を取って非製和会が入ることを情報共有して、機械の組立から施工1サイクルの試験杭が終わるぐらいまで、機材センターの担当者を常駐させて、作業所の担当者と一緒に非製和会の協力会社を指導する取り組みを今年から始めています。
基礎工事は、タイミングが作業所の立ち上がり時期で、所長が決まって次席が決まるかどうかぐらいで、その下で何も分からない新社員明けの人が担当することもよくあって、作業所の体制としては弱い時期の工事であると思います。
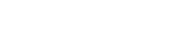 建設機械
建設機械